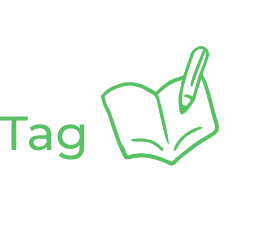公園にて
2021.5.25
「ただいまあー‼‼‼‼」「ただいまあ!」「ただいま!」とさくら組全員のただいまの声。玄関に行ってみると
「あのね、ダンゴムシがいっぱいいたんだよ!」
「たんぽぽ咲いてたよ!」
「鬼ごっこしたよ!」等々
聖徳太子にならなければ全部を聞いて理解できないほどの勢いで公園で遊んできたことを話してくれました。あとから、公園に行った保育者に聞くと、
・A君は草刈りをしているおじさんたちをじいっと見てい
て、見て!見て!と自分の手を思いっきり動かして草刈り機になっていたこと。
・大きな枝を公園の端から端まで運んで、たんぽぽで飾 り付けをしたこと。
・てのひらいっぱいにダンゴムシを拾ったこと。
青空の下、自然と100%仲良く遊んでいる子どもたち。目の前にある自然の中でただただ遊びこむこと。うらやましく思いました。コロナ禍にあって私たち大人にも大切な、必要なことではないかと思わせられました。
今日という日
2021.5.14
ようやく暖かな日になりました。子どもたちはクラス毎に体力に合わせ、公園へと遊びに行きました。
16日からの緊急事態宣言が決まり、新型コロナウィルスの感染が今後どのようになるのか?ここにきてまた、見えなくなってきました。様々な立場、様々な思い、様々な都合、事情がある中で、どのような対応が解決へと向かう方法なのか、わかりません。でも、確かに言えるのは、今日を精いっぱい過ごしましょう!ということです。それは子どもたちの方が上手です。どのような状況にあっても、そこで一生懸命遊びます。仲よくします。けんかをします。わがまま言います。泣きます。そんな子どもたちの日常を守っていくために、今私たちができることを一生懸命に探していくこと。それだけで幸せになります。市中感染が広がり、だれがいつどこで感染してもおかしくなくなりました。その中で互いを思い、相手の立場になり、今日を過ごしていくこと。この積み重ねが必ず、解決へと近づいているはず。と信じて‼‼
3月のお誕生会
2021.3.11
3月生まれのお友達のお誕生日会が無事に終わりました。感謝のお祈りの中に「み~んな4歳になれました。ありがとうございます。」この3月、クラスの中のお友達全員がお誕生日を迎えることができました。お誕生日が来ることが当たり前のように思っていますが、それはとても幸いな事。恵です。
事故や災害で予想していないことが起こることは私たちは様々な事柄からわかっています。でも、時とともに忘れてしまう者です。3月11日は10年前、東北地方太平洋沖地震がありました。その時に小学校4年生の子が「いつもの当たり前のことが普通の事ではなく、すごく幸せな事だったんだ。」とつぶやいていたことが未だに印象に残っています。
園児たちが全員無事にこの年、お誕生日を迎えられたことに心から感謝しています。生きてそこに存在していることは何よりもかけがえのないことです。元気な子どもたちにありがとう!そしてその子たちを慈しみ、育ててくださった保護者の皆様に感謝します。
一日入園
2021.2.2
今日は一日入園でした。感染対応をしながら、新入園の子たちも自らアルコール消毒をする習慣ができていて。環境の変化は人の習慣や生活を変えていくものだと思わせられます。いつもなら、在園児とフォークダンスや手遊びなどをしてかかわりを持ちながら、新しい子たちを歓迎していることを伝えます。でも、今回は写真でもわかりますが距離を取り、接触しないようにお互いをお互いが守りながらの一日入園でした。少し、春めいた明るい日差しの中で制限のある中でしたが、園に期待をもってもらえたのではないかと、信じて。
リモート研修
2021.1.19
北海道医療大学の教授の方からリモートで感染症対策についても研修を受けました。テレビや、教育機関からの情報から知識もそれぞれ得て、日々、感染予防を行っていました。にもかかわらず、やはり、直接お聞きして、質問し、すぐに答えていただけるのはとても勉強になりました。
今年度も3学期を残し、新年度に入りますが、新年度も保育や行事は今年度を踏まえ、感染予防対策をしながらの保育を考えていきます。制限の中でも子どもたちの方が楽しみ方はとても上手でした。であれば、想像力、感性を豊かに育てていくために保育者として腕を上げなければなりません。
講師からも最後に「先生たちも感染に気を付けて明るく頑張ってください。」とおっしゃられ、そこが基本だなと気づかされました。ある程度の見通しが立っている今なら、前を向き、明るく子どもたちを迎え、日々過ごせると勇気が湧きました。きっとこの気持ちの持ち方ひとつで今の時を子どもたちと、保護者の方々と乗り越えていけると思います。
クリスマス会 Ⅱ
2020.12.4
今日はクリスマス会の総練習。クリスマスの意味をそれぞれに知り、自分たちの役割をしっかり果たし、演じている子どもたち。ヨセフとマリア。羊飼いたち。天使たち。博士たち。王様と家来たち。難しいセリフも頑張っています。できることだけ、安心して行うことも、それぞれにちょっとできない事に挑戦しながら、乗り越えていく経験もこの年齢の子たちには必要です。みんなに観られて恥ずかしいことも、誉められながら、失敗しながら、できなくても認められていくことの小さな繰り返しの中で自己肯定感を少しずつ積み上げていきます。
「今日ね、幼稚園たのしかった!みんながねももさんの踊りを見てくれて、拍手をいっぱいくれたよ」こんな毎日を積み上げていけるよう更に一人ひとりの子どもたちをよく見ていきたいと思います。
そして例年と絶対的に違うのがマスクです。マスクを着けての”諸人こぞりて””きよしこの夜”今年の特色であり、天災等の災害と同等に忘れてはいけない新型コロナ感染。そしてここから学んだ多くのことを後世に残していく責任が私たちにはありますね。
参観日
2020.11.6
11月4日、5日、6日と参観日を行いました。いつもなら1日に全クラスの参観を行いますが、今回は3回に分散しました。各クラスに入っての参観は密になりますので、すべてホールで行える、リズム遊びや縄跳び、ゲームなど。できるだけ日常の子どもたちの姿が見られること。集団の中でその子自身がどう、関わっているか?を見ていただければと考えました。子どもたちは保護者の方々に見ていただいているので嬉しい反面、少し緊張もしつつ、何時もよりおりこうさん?で頑張っていました。ゆり組さんは前回お知らせした人形劇も観ていただきました。自分たちで考え、準備してきたものを観てもらうのはとても誇らしいと見えてそれぞれに自信をもって自分の役割をこなしていました。こうして自己肯定感が育っていきます。保護者の方の拍手に認められたことを確信し、次には何を展開するのか?楽しみです。
このひと時もいつもの何気ない1日1日の積み重ねの上にあります。ここにきて頑張れる、できるのではなく、生まれる前からのご家族の温かいかかわりの中から育まれてきたものです。子育ては今だけ見ると、変化のない退屈な繰り返しに思えますが、2,3歩後ろにさがってみると、それは未来に繋がるなくてはならない大切な1日の積み重ねです。保護者の皆様、毎日ありがとうございます。必ず、その手が祝福されます。子どもたちの成長に報われます。コロナ禍にはありますが必ず収束することを信じて。
人形劇
2020.10.28
”動物幼稚園のかくれんぼ”
今日は10月生まれのお友達のお誕生会でした。ゆり組さんが自分たちでお話を作り、ペープサートを作って人形劇を見せてくれました。9月の末に大きなホールでプロの俳優さんによる人形劇を見てきたのが刺激になって、子どもたち自身でさっそくお話しから、背景、小道具大道具と作り、今日の発表になりました。
さすがに自分たちが0から考え、造り、発表しますので、セリフの言い方や声の出し方、進行など、それぞれに自信をもって一人ひとりが生き生きと自分の役割を果たしていました。
どうしても発表会などは指導側から降ろしていったお話しや役割、そして練習と子どもたち自身の創造性、想像性、自主性を育て、引き出していくことが難しくなっていきます。今回の発表を観て、子どもたちの自発的な活動から保育が創られいく様子を見られ、そこに確実に成長し、豊かな日々を過ごしていることが伝わってきました。
地震避難訓練
2020.10.20
地震避難訓練を行いました。毎回行う中で、足りないことや、必要なことにを気づかされ、子どもたちよりも私たち教職員が踏まえていなければならないことが多いことに気づかされます。何度か重ねてきた中で、今日は1回目の地震の後もう一度揺れが来て、外に避難をするまでを計画しました。「地震だよ。ダンゴムシになるよ!」の言葉に子どもたちは素早く頭を抱えてダンゴムシになるようになってきました。その後、子たちの点呼をしてその時点で来ている子たちの確認をします。20分後くらいにもう一度揺れが来てダンゴムシになり、点呼をして外へと非難をする。
やはり一番大事なのは日頃の保育者と子どもたちとの信頼関係だと感じました。訓練ですが真剣に行う保育者たちの言葉に子どもたちはちゃんと聞いてその通りに行います。子どもたちのいのちを守るには大人だけではできません子どもたちがこの先生たちについていこうと思わなければ成り立ちません。子どもたちが真剣に話を聞いて、誰一人泣き出す子もなく、保育者の手順もしっかりできて、少し安心できました。ただ、災害は忘れたころにやってきます。忘れることなく、備えはしますが、来ないでほしいと願いつつ。でもいつ来てもあわてないよう、子どもたちとの信頼関係、教職員間のチームワークを日頃から育てていかなければと思わせられました。
お祭りごっこ
2020.10.19
先日、ゆり組さんが小さい組さんたちにお祭りの縁日ごっこをして遊んでくれました。”夜までいっぱい遊ぼう会”で自分たちが遊んで楽しかったことを、伝えたくてやってくれました。カードのくじ引きから景品も自分たちで手作りした、奴さんや風車。準備のところから、みんなへの説明後片付け。さすがゆり組さん!と拍手を送りました。自分たちが楽しんだことを誰かに伝えたいという思いと、それを自分たちで計画し、行っていく。本当に人として必要な、自分たちで考え、実行していく力が育っていると嬉しくなりました。さくら組、もも組、ひよこ組の子たちもゆり組さんの説明をしっかり聞いて遊び、心から喜んでいる姿が伝わってきました。自分のことは自分で、から更に先の周りの人たちの喜びのために何かをする。順調に、それ以上に育っているゆり組さんに感謝です。