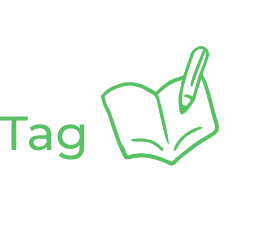クリスマス
2019.12.25
メリークリスマス
今年もクリスマスですね。私は小さい頃、クリスマスに嬉しいプレゼントをもらった記憶がありません。私の年令だと皆さんそうなのかも知れません。でも大人になってクリスマスを迎えると、周りの方々にプレゼントするのが楽しくて、ささやかですが、何かかにか贈り物をするのがこの頃の私のクリスマスです。受けるより与える方が幸せを感じることも多くあります。ものではなくても親切や思いやりやお手伝い。自分と同じように隣人を愛せることを喜ぶクリスマスはすてきだと思います。朝、登園してきた園児がサンタさんにおもちゃをもらったと、とても興奮して聞かせてくれました。きっといつか、送る側の喜びも経験できると信じています。良いお年をお迎えください。
お弁当箱
2019.12.19
今は給食を行う園が多くなってきました。働くお母さま方、様々なご事情がある方々のために、今はとても必要になってきました。
自分が教諭になった頃、研修の中でお母さんたちは「かえって来たお子さんのお弁当を開けただけでその日のお子さんの様子を読み取ります」とお話ししていました。給食になるとそこが見えにくくなりますが、きっとそれぞれのお子さんのサインがあるはずです。日頃の日常のお子さんをよく見ていれば、必ずわかってくるはずです。
なんでもインターネットを調べれば数秒で回答が出てきますが、お子さんの心の状態、体調はそば近くでにいる保護者の方でなければわかりません。お子さんと関わる時がいつも大切にできるとよいですね。
固まってていいよ
2019.11.22
5歳のR君がお母さんに「お母さん。固まってていいよ。」と言ってくれたことを聞きました。
主婦の皆さんは朝から夜寝るまで、食事の事、家族の着ていくもの、持ち物の事、洗濯、明日の用意等、多岐にわたって準備し、予定を確かめてお子さんやご主人の1日1日が平和に過ごせるよう、配慮しています。きっとお子さんの前でも、忙しく、気配りをしながら、動き回っている姿があるのでしょう。
そして乳幼児はできるだけ母親が自分の方に向いていてほしくて、要求してきます。用事がなくても何か作って自分の方に向けようとします。そこで信頼関係を築いているので、それも大切なことでもあります。でも、R君はお母さんに対して、「固まってていいよ」と言えました。お母さん、今は何もしなくていいよ。お母さんの時間にしていいよ。という意味で言ってくれたというのです。大きく一つ成長したと感心しました。自律の一歩ですね。
そして、もう一つ。忙しい生活の中で、ふと、立ち止まるときがどんなに大切なことか。次へ次へと仕事をこなしていく流れを一度ストップさせて、周りを、自分を見つめてみること。そんなに急ぐ必要はなく、明日のことは明日心配すればよいこともたくさんあって。自分の心に向き合う時間をゆっくりとる事。固まる時間を私も作っていこうと思います。R君ありがとう。
みんなが仲良く暮らせるように
2019.11.15
「みんなが仲良く暮らせるようにならないものでしょうか?」とニュースキャスターが言われていました。当園のクリスマスペイジェントにも「みんな仲良く暮らせるようにならないかなあ」というセリフを開園当初から使っていました。
教育や人命救助の現場で行われているいじめの報道。耳を疑ってしまいます。いじめをしてはいけない!と教えなければならない大人たちが行っているいじめ。聖書には「自分の敵を愛しなさい」「隣人を自分と同じように愛しなさい」とあります。自分の敵とまで言わなくても意地悪されたり、嫌なことをされたら、同じくらいのことを仕返ししたいと思いますが、意地悪されたら親切でお返ししなさいと説きます。自分ができているか?と言われたら、難しい所です。大人の背中を見て育つ子どもたち。すべての人を自分と同じように愛することはできませんが、害を与えたり、傷つけることをお互いに避ける努力をしていけば、いじめは少なくなるのではないかと思うのですが…子どもたちにいじめるなという前に大人たちがまず自分の周りの方々と良い関係を結んでいく努力をしなければならないですね。自分の反省も含め、皆さんが仲良く暮らせるように!切に願いつつ、努力します。
出会いに感謝
2019.11.5
先日、北光幼稚園の創立100周年記念礼拝、記念講演に出席させていただきました。記念講演の講師は私が元北星学園幼稚園教諭保母養成所でお世話になった担任でした。(今から40年前です。)懐かしくお会いし、まだまだお元気なお姿に励まされる思いでした。ご自身の研究を探求し、今も現役で研究されているお姿はとても刺激になりました。そして、今現在同業者であり、やはり担任をしていただいた友と一緒に講演前にあいさつに行きましたが、今も幼稚園教諭として立っていることを伝えられたことがとても誇りに感じました。そして、一番感謝なことは、保育者、教諭となって35年以上たちますが、その原点で出会った方にお会いできたこと。そして、一人でここまで来たとは思っていませんが具体的に、自分の今現在の土台、根っこのところで支えられていたことを再確認させられ、感謝が溢れました。今豊かに祝福されていることは、もうずっと前から計画されていたことで、偶然ではなく、導かれていたんだと。出会いの一つ一つが自分を造り、今を生かしていただいているのだと感激しました。
教諭の仕事をさせていただいている以上、自分自身も相手にとって良い出会いだったと感じてほしいと、更に自分が学びの手を休めてはいけないと襟を正されました。
中学生訪問
2019.10.25
今日は中学3年生のお兄さん、お姉さんたちが家庭科の授業の中で訪問してくれました。紙芝居や魚釣りなど、手づくりをして何日も丁寧に準備をしてきてくれたことが伝わってきました。グループに分かれて、それぞれがよく関わられるように、考えられていました。園児たちもお兄さん、お姉さんたちととても仲よく喜んで遊んでいました。卒園生たちも何人かいて、その成長ぶりには目を見張るものがありました。子どもたちの成長を見るのはとてもとても嬉しいことです。
一つ気になったことがありました。それは事前に家庭科の先生と打ち合わせをしていた時のことです。自由な時間があると何をしていいかわからず、不安になる子がいるということでした。園児たちは毎日、許された守られた空間と時間の中で自分の好きなことを自分で選び、気のすむまで遊びこむ。そこには何の縛りもありません。失敗もします。何回もやり直しをします。友達とのトラブルも日常茶飯事です。その中で迷惑をかけてはいけないことや、破ってはならないルールがあることを学んでいきます。そこから、生きていく意欲、好奇心、想像力などが育ち、主体的に生きていけるようになると考えます。せっかく育った芽が枯れてしまわないか心配になります。自由な発想や行動が互いに受け入れられる環境を自分自身が作っていくこと。少数、多数に関わらずそれぞれの思いが受け止められていく社会になってほしいと願います。
忘れ物
2019.10.18
よく、忘れ物検査などをして忘れ物をしない意識を高めたり、時間割をなんども確認する習慣を付けたり。保護者が低学年のうちはしっかり見てあげたり。でも、今の忙しい社会においては、保護者の方々も子どもたちの準備に対してままならないところがあるようです。忘れ物をしないことは大事なことですが、幼児期、小学校の低学年のうちの忘れ物は取り返しがつくものです。取り返しがつくうちに何度か、忘れ物やほかの失敗をすること。そしてその失敗をどう乗り越えるか?というを経験して育ってほしいと思います。忘れ物をしたとき、失敗したときの思いは皆さんも経験があると思います。それぞれに感じ方は違いますが、自分が我慢しなければならないことや、周りに迷惑をかけたことへの申し訳なさ、どうやったら取り戻せるか?考えること。失敗には非認知能力をフルに使わなければならない面が多々あります。あえて、忘れ物をする必要はありませんが、子どもたちが自分で準備して、いくつかの不足があった時に全てを周りが整えるのではなく、失敗する経験をすることが大切です。そこから学ぶこと、成長することがたくさんあります。失敗する恥ずかしさを乗り越えながら、人は大きくなります。マニュアルでしか考え、行動できない大人に育てるのではなく、子どもたちには予想外のことが起こった時に目の前にある状況から、打開策をみつけ、進んでいけるよう、クリエイティブに育ってほしいと切に願います。
どっちにする?
2019.6.4
何かを選ぶときに選べない人がいます。今日着ていく服や、どのケーキを食べるか等を決めるのはそれほど後々に大きな影響はありません。でも、日々の中で、家族の健康に関わる事や、将来に影響する判断もあります。前にも書きましたが、毎日の中での何げない小さな決断が大きな決断をする訓練になります。そして子供は親がどんな判断をしているかを見ながら成長して行きます。でも、今は選択する力量や知恵がないうちに子どもたちに多くのことを選ばせているような気がします。朝、子どもの様子を見て園を休ませるかどうか?子供に聞いて判断する保護者がいると何かで読みました。保護者のかたがたにも今からでも遅くありません。判断には責任が伴いますから、そこを避けたい方々が多数であることはよくわかります。でも、お子さんたちが人生を豊かに生きていくためには様々な多くの判断が必要です。その判断ができるように育てていくには今この幼児期の小さな判断の積み重ねです。そしてそれはまだまだ間違ってもいいのです。間違ったらまた、やり直せばいいのです。保護者が判断するところや間違ってもやり直して前に進むところを見せていくことで、子どもたちも失敗を恐れずに進んでいける子に育っていきます。失敗をしてもまた、そこから違う方法で進んでいけます。どうか大いに間違ってください。そしてやり直すことは恥ずかしくないことをお子さんたちにちゃんと伝えてください。それが家庭の教育力です。応援しています。大事なのは間違えることなく成功することよりも間違えた時にやり直すことができることです。
一期一会?
2019.5.13
「一期一会」一生に一回限りのこと。生涯にただ一度会うこと。と辞典にあります。
いつも会っている家族や友達。日常の中では誰ともいつでも会えると思っています。幼稚園で朝出会ったお子さんがそのままの姿で帰せるように祈りつつ、願いつつ保育をしています。でも、不慮の事故はどんなに環境を整備し安全に整えても起こるときには起こります。これだけは絶対におこらないように願いつつ細心の注意をもって保育に当たります。
今回の大津市の事故で掛け替えのないお子さんをなくされたご家族にとっては信じがたい出来事でした。一生に一度しか会えない方に心を込めて、お茶を差し上げること。これは毎日会える家族や友達にもその思いをもって大切にもてなし、関わっていくことがとても大事ではないかと思わされました。毎回会える方にも、家族にも今できる限りのことをしてあげること。でもそれには限界もあります。そしてできれば失敗したとき、傷つけてしまった時には次回に謝ることができる機会が与えられることを切に切に願います。すべての尊い命が大切に守られますようにと願わずにはいられません。
尊い命
2019.5.10
大津市においての保育園児の事故で尊い命が失われました。失われた命に対する思いはどんな言葉でも表せないほどの悲しさ、苦しさ、悔しさ、怒り、理不尽な思い…でも当事者であるご家族や保育園関係の方々の思いはいかばかりかと察するに及びません。今はこのような事故が起こるとすぐに責任問題や賠償、再発の防止とどんどん先へ先へと進みます。今回は散歩の自粛の考え。今までにブランコの事故や滑り台の事故があれば、その遊具の撤去等。そうではなくて、今回は運転者の運転意識が問題であり、また、運転するもの全員がいまもう一度、ハンドルを握ることは命に係わる重大な責任を伴うことであることを認識することではないかと思います。私自身、自分の運転を見直し、殺人マシンに乗っていることを自覚して運転することをもっともっと心がけなければならないと再確認しました。けがをしたから、事故を起こしたから、その保育内容を見直したり、遊具を撤去するのではなく、どう遊んだら、安全に遊べるか?小さな失敗、小さなケガをしながら大きな失敗、大きなけがにならない訓練としてこの幼児期を様々な経験をさせることは大切だと考えます。ただ、今回のように取り返しのつかない事故に巻き込まれた時には、どう判断し、慰めの言葉も浮かびません。ただ、ただ、子どもたちの遊びの範囲が狭められないことを願っています。