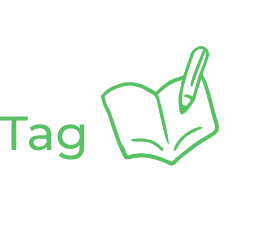1年の感謝
2025.12.26
本日で2025年の保育は終わります。年度は3月終了ですが。保育者間の話の中で「今から20年後ってどうなっているのだろう?」まだ、私たちの子どもの頃は、自分がなりたいものややりたいこと。自分の前を歩いている方を見て、夢を持っていました。でも、今は世界の情勢の不安や異常気象。そして、今までに考えられなかった事件や事故が年々増えていく中、本当にどうなっていくのだろう?と。災害もいつどこで何か起こるかわからない。そう考えると本当に不安になります。新しく迎える年がどのようになるのか?でも、悲観、心配ばかりしていてはこれから成長し、夢を実現しようとしている子どもたちにマイナスのイメージしか与えられません。私たちは特に子どもたちと共に歩むには私たち自身が夢を、希望を持つ必要があります。子どもたちが豊かに育つためには私たち大人が夢を持ち、未来を少しでも明るくしていく事。まずは自分の周りに平和を築き、それを広げる事。来年の目標の一つに加えませんか?一人ではできないけれどみんなでお行えば、その和は広がります。子どもたちの未来を明るいものにするために!今年も色々お世話になりました。良いお年をお迎えください。
おのまとぺ
2025.12.16
先日出た研修の中で「日本語ほどオノマトペが豊かな言語はない」と言うことを学びました。基本的な生活習慣を教えるにも、「シーシー」(おしっこ)、「あむあむしてね」(よく噛んでね)等日頃の子どもとの会話の中にたくさんありました。また、雪が降ってくる表現にも「ふわふわ降ってきた。」「ほわほわ降ってきた。」とニュアンスが少し違ってくる感覚があります。ほわほわの方が少し温かみがある感じ。この感じが大切だと思いました。言語では伝えきれない、目に見えない心の何か?が伝わっていく事。感じること。それができる日本語の豊かさに改めて感動させられました。
絵本のおもしろさ
2025.11.14
今朝、11月の月刊誌を読みました。スウェーデンのお話でアンナ.マリア.ロースという方が2才から4才の子どもたちのために100年以上前に書かれたものでした。読んで私は「え?どこがおもしろいの?」と思い、解説を読んでみました。そこには「出てくる白猫とフクロウのやり取りのコミカルさ、ユーモア。対象の子たちが読み取れる語彙を使っている」とありました。私のかたい感性がこうべを垂れました。絵本に限らず、芸術や小説等様々な作品や、考え方はそれぞれで、自分が見ている方向だけで判断してはならないと感じました。今までも知ってたはずなのに…意味があるか?面白いか?役に立つか?等は見方によって、立場によって、年齢によって、環境によって多種多様に変わってきます。その絵本を単純に楽しめなかった自分の感性の貧しさを悔しく思い、またそれも、固い考え方だなと更に感じました。面白くないものには面白くないと言っていいと思いますが、少し違う角度から見たら、違う感覚や考え方にも出会えて、視界を広げられるのだと、今更ながらに考えさせられました。
お互い様
2025.11.10
先日テレビの教育的番組を見ていましたら、講師の方が「日本人は相談する方々の率が世界の中でとても低い」と言うお話をされていました。しつけや育て方の中で、日本人は「人に迷惑をかけないように!」「自分の事は自分でしなさい。」と言われてきました。確かに迷惑をかけることはできるだけ避けなければなりませんが、家族の中で何か困っていることがあれば相談してほしい。助けになりたいと思うのは皆さん同じです。いじめなど相談できずに自死に至ってしまうのも、相談することがどこか、恥ずかしかったり、迷惑、心配をかけられないという思いの表れではないでしょうか?乳幼児期の今は当たり前のように、甘えて、世話をかけ、面倒を見るのは当然です。確かに社会人として自立するための備えや教育が必要ではありますが、それは全て自分で考え、自分で決断して実行していくということではありません。必要なことは早めに相談することや悩みを打ち明けることは恥ずかしいことでも迷惑なことでもないということ。逆に早くに相談してほしいと保護者の方々は思っていると思います。相談しやすい話しやすい環境をご家族や地域で作っていく必要を感じました。
ままごとあそび
2025.10.23
0才児クラスでのままごと遊びのことです。0歳児と言っても1才2ヶ月のUちゃん。ままごと遊びが大好きです。茶碗にご飯に見立てたおもちゃを入れたり出したり。出したり入れたり。おいしい料理を作って並べています。時々私に蓮華にのせた食べ物を、どうぞと言いたげにくださるので、ありがとうといただきます。ある時はぬいぐるみを布団に寝かせ、背中をトントントントンしています。0才なので、まだまだ何も知らないと思ってしまいますが、もうすでにちゃんとご家族から受けている愛情を遊びの中で実現しています。保護者の方の温かさ、やさしさ、強さはもうすでに伝わっています。この時期にちゃんと愛され、守られ、ご飯を食べておなかをお満たし、身の回りをお清潔にしてもらい、温かい腕の中で安心して過ごす。この当たり前のことが本当に人として成長するためにとてもとても大切なことです。確かに良い学校、良い教育を受けさせることも大事だとは思いますが、いま、この時に十分に豊かな愛情の中で育て、関わることが人として育つため大切なことです。お子さんたちと良い時間をお過ごしください。
お茶
2025.10.8
当園では30数年前から、1ヵ月に1回、年長さんがお茶の時間をもっています。年間を通して一人でお茶のお点前ができるようになり、お友達に点ててあげたり、ご家族の方をお招きしてお茶会ができるようになります。お茶の先生の言葉を聞きながら、袱紗をさばき、棗、茶杓を清め、お茶を点てます。何かを初めて行う時、今は大人もインターネットや動画を見ながら行いますが、子どもたちは耳からの言葉を理解してお点前をしていきます。耳で言葉を聞き、舌でお菓子の味を楽しみ、点てたお茶の香りをきき、背骨をまっすぐにしておなかに力を入れて茶筅を振る。体の全て、五感のすべてを働かせている姿が感動です。それも無理なく、とても楽しんで取り組んでいます。3月にご家族の方々にふるまう時が今から楽しみです。お茶を取り入れたのは、日本の伝統的な素晴らしい文化に幼児期に触れてほしいと考えたからです。時短、便利な方法が好まれる今ですが、時間をかけながら、相手の為に心を込めてお茶を点てる。大切にしたい保育の時間です。
風の子さん
2025.10.6
今日は”劇団風の子北海道”さんが子どもたちに「みんなでぬくぬく」と言うお話と大型積み木遊びをしてくれました。積み木遊びはレンガの2倍くらいある手作りの積み木を使って、動物に見立てたり、ストーブや椅子などにして遊びをお広げたり。新聞紙でも様々な遊びを展開してくれました。いつもテレビやユーチューブ等で映像と音を同時に聞いている子どもたち。全てシンプルな積み木で作られる動物や電化製品の見立てを最初に言い合てたり、演者の方が困っている様子を見せるといち早く積み木で何を作ればいいかを次々に発言していました。やはり、考えようとする、発想しようとする環境があれば、子どもたちはちゃんと想像し、イマジネーションをはたらかすのだなと感心しました。でも、そこに甘んじず、想像力が培われるような環境づくりを努力していきたいと思いました。
収穫感謝の会
2024.10.18
今日は収穫感謝の会でした。収穫の恵み、日々の守りを園児と教職員で神様に感謝します。日々の守り、普通の日常の生活は当たり前でなく、一つ一つ感謝なことであることをこの時に確認します。日本では水道から飲める水がすぐに出ることが当たり前でも、水を遠くまで組に行かなければならない国や、子どもなのに家族のために働かなければならない国。まだ子どもなのに結婚しなければならない国等。様々な国の様々な事情を知り、子どもたちと考えその意見を聞きます。子どもたちなりに自分たちの置かれている所を理解し、世界の国々に目を心を向けて感心をもっていきます。3才、4才、5才の子どもたちが精いっぱい考えて、汚い水しか飲めない国の子のためにお祈りをします。戦争の中で大変な子たちのためにお祈りをします。自分の事だけではなく、隣のお友達の必要に気づき、祈ってあげるところから始めていきたいですね。
布おむつ
2024.10.16
認定こども園へ移行するにあたり、おむつを布に替えました。“手ぶら登園”とし、朝はご家庭から紙おむつで来ていただき、園で布に取り替える。帰りにまた紙おむつへと取り替えて帰ります。園内でその日使った布おむつは業者さんが洗濯してくれるので、保護者の方々の手間はありません。多少、費用は掛かります。でも、この4月に入園した1才の子たちはこの8月前後でお兄さんパンツへとなり、おむつが取れました。多少の費用は掛かりますが、おむつがとれる時期がはやまりますので、紙おむつの購入費はなくなります。やってみて私も驚きました。こんなにおむつが取れるんだ!と。布おむつにする一番の目的は快不快から生まれる人としての豊かな感情、感性の育みです。不快な濡れたおむつから、気持ちの良いおむつへと替えてもらった時の心地よさによって相手との信頼も深まります。
始めてわかったのは、意外に布おむつに関心のある方々が多いということです。子育ては手がかかります。人を育てるのですから。できる範囲でかけられる手間と時間。幼いうちは特にかけられた子どもたちは幸せ者だと思います。
こんにちは!
2024.10.16
この4月より認定こども園へ移行しました。幼稚園からの変更ですので、0才、1才を保育するのは初めてです。戸惑いつつ・・・経験のある保育士たちの丁寧に保育している姿や、内容を見、教えられながら、私も少しお手伝いをさせていただいています。生後3か月から保育する日々の保育の中で成長の1つひとつを共感できることの尊さを感謝しています。
首が座って、寝返りを打てるようになり、一人で座れるようになり、両手を使っておもちゃで楽しそうに遊ぶ。朝の挨拶を元気に交わし、絵本にも喜んで応答してくれる。その一つひとつが成長の表れであり、生きる力を育んでいるのだと実感させられます。
この1日1日の積み重ねから3才、4歳へとつながり、人として大きくなっていく。大切な一人ひとりとの毎日の関りがかけがえのない尊いものと実感させられています。