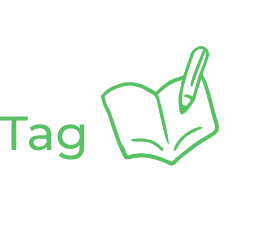クリスマス
2019.12.25
メリークリスマス
今年もクリスマスですね。私は小さい頃、クリスマスに嬉しいプレゼントをもらった記憶がありません。私の年令だと皆さんそうなのかも知れません。でも大人になってクリスマスを迎えると、周りの方々にプレゼントするのが楽しくて、ささやかですが、何かかにか贈り物をするのがこの頃の私のクリスマスです。受けるより与える方が幸せを感じることも多くあります。ものではなくても親切や思いやりやお手伝い。自分と同じように隣人を愛せることを喜ぶクリスマスはすてきだと思います。朝、登園してきた園児がサンタさんにおもちゃをもらったと、とても興奮して聞かせてくれました。きっといつか、送る側の喜びも経験できると信じています。良いお年をお迎えください。
スウィートポテト
2019.11.27
今日は11月生まれのお友達のお誕生会でした。毎月、手づくりのおやつを考えます。季節に合わせ、アレルギーの方々を考えます。秋はジャガイモをふかしたり、カボチャはスウィートパンプキン、サツマイモでスウィートポテト。今年は幼稚園の畑でサツマイモがたくさん採れました。そのサツマイモを使ってのスウィートポテトを作りました。さすがにお店で売っているものよりは灰汁も強く、形も悪く、大きさも細いものが多く、なんと扱いにくいことか?それでも自分たちで収穫をしたサツマイモ。人数を考えると、レシピ本を開くより、すべて感?砂糖もバターも塩加減も。
食べている子たちは口々に「おかわりないの?」「先生明日も作ってね」と言ってくれて。この言葉を聞くと、扱いにくさも、灰汁の強さもなんのその。またおいしいものを作ってあげたくなります。畑をおこし、苗植えから、畑を管理してくれたバスの先生にも感謝!
食育には五感のすべてを使います。見た目の食べやすさやおいしそうな色。食べる時の音、食材を用意する時の切る音、煮える音。匂い、味、温かさや冷たさ。台所から、トントン、シューシュー、チン!と音が聞こえ、良いにおいがしてきて、おいしいものができてくる。おいしく食べて、五感とともに心と体も満たされて、家庭の豊かさも感じていきます。家庭の中の豊かさとは経済的なものではなく、こんな些細なことから、信頼関係がうまれ、自分はここに居ていいという自己肯定感も生まれることではないかと思います。お忙しい方々が多い毎日ですが、時々は家庭内での音やにおいから始まりおいしいで終わるプロセスが繰り返されるといいですね。
中学生訪問
2019.10.25
今日は中学3年生のお兄さん、お姉さんたちが家庭科の授業の中で訪問してくれました。紙芝居や魚釣りなど、手づくりをして何日も丁寧に準備をしてきてくれたことが伝わってきました。グループに分かれて、それぞれがよく関わられるように、考えられていました。園児たちもお兄さん、お姉さんたちととても仲よく喜んで遊んでいました。卒園生たちも何人かいて、その成長ぶりには目を見張るものがありました。子どもたちの成長を見るのはとてもとても嬉しいことです。
一つ気になったことがありました。それは事前に家庭科の先生と打ち合わせをしていた時のことです。自由な時間があると何をしていいかわからず、不安になる子がいるということでした。園児たちは毎日、許された守られた空間と時間の中で自分の好きなことを自分で選び、気のすむまで遊びこむ。そこには何の縛りもありません。失敗もします。何回もやり直しをします。友達とのトラブルも日常茶飯事です。その中で迷惑をかけてはいけないことや、破ってはならないルールがあることを学んでいきます。そこから、生きていく意欲、好奇心、想像力などが育ち、主体的に生きていけるようになると考えます。せっかく育った芽が枯れてしまわないか心配になります。自由な発想や行動が互いに受け入れられる環境を自分自身が作っていくこと。少数、多数に関わらずそれぞれの思いが受け止められていく社会になってほしいと願います。
先生、あのね
2019.10.3
「せんせい、あのね、この靴下おかあさんに買ってもらったの。」
「せんせい、あのね、今日ばあばとプール行くの。お兄ちゃんとおねえちゃんも。」
「せんせい、あのね、これ虫なの。でね、魚になっちゃうんだよ。そしてね」
満3歳の子との会話です。向き合ってゆっくりじっくりきいていると、延々続きます。お話はとりとめもなく、本当の出来事とそうでないものとが混ぜ混ぜになっていますが、楽しそうにたくさん話してくれました。
聞きながら、この時期の子たちはこうして自分の話を聞いてもらいながら、自分の存在を確かめているんだなあと感じました。この子にとってこの記憶はきっとひとかけらも残らず消えてしまいます。でも、受け止めてもらったことは魂、情緒が受け止めます。乳幼児期の大切なところはここだと思います。何気ないまいにちですが、その中で普通の事。朝起きてごはんがあって、洗濯されたものを着て、遊び、1日を過ごす。周りに自分をまもり、育んでくれる方々がいてくれる。その日々の中で健全に心身は成長していきます。その積み重ねを通してお子さんたちは自分が保護者の方々に愛され、存在していていい、大切な者だと自己肯定していきます。今の、今しかない乳幼児期をできるだけゆっくり向き合う時間をとり、楽しんでください。私たちも微力ですがお手伝いさせていただきます。
火災避難訓練
2019.6.26
昨日は火災避難訓練でした。消防の方々にも来ていただき、消防自動車は2台も来てくれました。火事を発見し、初期消火をし、子どもたちの誘導、消防署への通報等、一連の流れは毎年行っていても緊張します。また、実際に火事が起きた時にはどう動けるか?訓練をちゃんと生かせるように取り組みたいと考えています。また、園児たちは練習だとわかりつつも非常ベルの大きな音が怖かったり、いつもと違う動きに戸惑ってりと、初めての子たちにとっては訓練といっても真剣な取り組み事項です。
一通り終えて、消防自動車を見せてもらって、質問をしました。Sちゃんが「消防自動車は怪獣をやっつけられますか?」と聞きました。消防のおじさんは「やっつけられるように頑張ります」と答えてくれて一安心。大きな消防自動車は火事からも、危険からも私たちを守ってくれます。でも出動しない事件事故のない平和な日々を心から祈っています。また、子どもたちの小さな質問?夢も守ってくれたことに心から感謝です。命を守られる事と、自分の命を自分で守ることの大切さを知った1日でした。
空想のおはなし
2019.5.8
私 「おはよう」
A君「今日ね。夢見たんだよ」
私 「どんな夢見たの?」
A君「怪獣出てきたの」
私 「怪獣怖かった?」
A君「怪獣仲良しだった」
私 「何して遊んだの?」
A君「ブロックで消防車作ったの」
B君「僕もね、僕もね夢見たよ。」
私 「誰出てきたの?」
B君「アンパンマンとばいきんまん」
と満3歳の男の子二人と私の朝の会話です。この後もお話はどんどん膨らんでいきました。夢をどれだけリアルに覚えているのかはわかりませんが、聞かれたことに様々に考えて答えてくれました。もう一人の子もその会話に入りたくてちゃんと話の中に入ってきました。うその作り話としてしまうのではなく、昨今想像力の低下が心配されている中、満3歳の子にはこんなに想像力が豊かにあります。これを更に豊かに育てていくことが私たちの大切な責務です。お子さんたちと想像を膨らませられるお話しをたくさんしましょう。その中で現実との違いも分かっていきます。満3歳児の時にはちゃんと想像力が備わっています。これを日々の何気ない会話の中で育てていきましょう。
大型遊具
2019.4.26
今日から園庭に工事が入りました。大型の遊具を計画しました。砂場と泥で遊べる所。
クライミングができる所等。保育者たちと子どもたちが様々な遊びが展開でき、体を動かし、心を動かして遊べることを目指しました。業者さんともいろいろ話し合い、アイデアをもらって、昨年秋から着工しました。今朝、大きなと落暉からクレーンで運び出された10本の10mくらいの丸太。保育室から見ているとすごい迫力で子どもたちはくぎ付けでした。素材からできていく様子を見られることも予期せぬ収穫でした。こんなに近くでクレーンや丸太を見るのは私たちも初めてでした。完全な感性は来年になりますが、今期は5月末で完成です。どのような遊びが繰り広げられるかわくわくドキドキです。
遊びって本当に楽しく心躍りますね!
かくれんぼ
2019.1.23
「もーいーかーい」「まあだだよー」「もーいーかーい」「もーいーよー」
満3歳児のかくれんぼ。まだまだルールが理解できない、ルールがあることさえもわからない。自分のやりたいこと、自分が良いと思えればそれでいいと考えている幼児に、鬼の意味、隠れること、見つかったら次に鬼になることなどは何度も同じように遊びながら、覚えていくことです。最初は「もーいいかい」の答えに「もーいいかーい」と返し。かわいいのは自分が目をつぶったら見えないので、そのまま自分が隠れられていると信じ目をつぶり、じっとしゃがんでいる子。とても愛らしく、見つけてもそのまま見続けていたいと思うほど。子どもたちが遊びの中でまず、ルールを覚える前に友達や先生たちと楽しく遊びこみ、見よう見まねで覚えていく所、自分たちなりに約束を作って遊び、理解できるようになっていく中でルールがあった方が楽しく遊べることを学んでいく。また、楽しく遊べるためにどうすれば良いか友達の間で約束事を作っていくことの経験がとても大切です。子どもたちが想像を膨らませ、遊びを自分たちで展開させていくことが幼児期にはとても重要です。そしてそれが一番楽しい遊びにもなります。
キリスト教保育
2019.1.22
「ここでこの本読んでいい?この絵本大好きなんだ」と年長のIちゃんが職員室に来て、
ソファーに座りました。たどたどしく声を出して読んでいる絵本は「十字架への道」です。
聖書に書かれているイエスキリストの十字架の場面の絵本でした。絵本とはいっても内容は幼児期の子には難しいものです。「どうしてイエス様は死んだの?」と聞くIちゃん。「みんなの罪のために十字架にかかられたんだよ。でも死んだままではなくよみがえられたんだよ」
罪、死、よみがえり。どの言葉も幼児には難しくすぐには理解できないものです。でもその子の「この絵本好きなの」と持ってきた背景には絵本の正確な内容というよりも、いつも聞いているイエス様のお話。そこには愛があふれ、暖かな空気を感じている。当園は祈りで始まり祈りで終わります。自分の力以外に支えてくれるものがあることを感性でとらえていく中、内容はわからなくても、心には落ち着くところがあるのだと感じます。
幼児教育は何かを教え込んだり、何かができるまで訓練することよりも、自分が受け止め支えられている。失敗してもできないことがあっても存在していていい。その子自身の存在が尊いのだということを心と体でしっかり感じ取っていくことが大事で
す。キリスト教保育はまさにその一人ひとりの存在を認めていく保育です。
クリスマス Ⅱ
2018.12.21
今朝の礼拝の中で子どもたちに「クリスマスはどうして嬉しいの?」と聞いてみました。「プレゼントもらえるから」「サンタさんくるから」そして「イエス様が十字架にかかってくれるために生まれた誕生日だから」と今までの習慣であった楽しさと、クリスマスの本当の意味を礼拝の中で聞いていた子たちの素直な答えが返ってきました。
小さな子どもたちにとってはまだまだプレゼントをもらう側。ツリーの下に置かれたプレゼント。目を覚ましたら枕もとに置かれているプレゼント。
わくわくドキドキします。期待の中にある子どもたち。その子たちに今日はもう一つ。「もらうだけではなく、みんなにもできることをしてみようか?」
ということで、いつも守ってくれている保護者の方々へ、日々の感謝を伝えることはとても大切で、お母さんお父さんにとっては感謝されることはとても嬉しいことであることを伝えました。クリスマスはどうしてもサンタさんやケーキやごちそう。プレゼント交換などがメインになりますが、お互いに感謝しあうことが何よりの喜びだと考えます。もうすでに神様がイエス様を私たちのために与えてくださったのですから。思い通りにいかないこともまだまだ目の前に課題としてあるかもしれません。でも、今、在ることだけで、感謝であることに気づけることが大事ではないでしょうか?
今年は9月に大きな地震がありました。そのことで子どもたちも私たちも多くのことを学び、今までとは違う思いで日常を送っています。そして普通に送っているこの日常が当たり前ではない特別な祝福であることをもっともっと深く知ることが出来ました。
今年の特別なクリスマス。誰にどんな感謝を伝えますか?