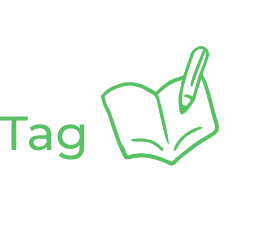初めてのお茶
2015.5.22
年長組は月に1度お茶(裏千家)のお点前を習います。3月には保護者の方をお招きしてお茶とお菓子でおもてなしをします。
今回は初めてでしたが、とても良い緊張感の中、先生のお話をしっかり聞いて取り組んでいました。
準備の時に、私が抹茶をこしているとYちゃんが「何をしているの?」と見にきました。「お茶の準備だよ」というと緑の粉を見て「お茶の用意?」こしたお茶を顔に近づけてあげると、「あっ!葉っぱの匂い」「そうそうお茶は葉っぱからできているからね」そう答えながら、大人はこの粉を抹茶と知っているからこの
かおりは抹茶のかおりと決めつけてしまっていますが、子どもはそれを素直に原体験から「葉っぱの匂い」と感じました。子どもたちの素直な感性に目が覚まされたような気がしました。
彩雲
2015.5.18
今朝、火災避難訓練をしました。初めてなのにみんなとてもよく先生のお話を聞き、おしゃべりをせず、泣きもせずに訓練が
出来ました。
その時に空に架かった彩雲。こんなにはっきり、大きく長い間
かかっているのを見るのは初めてでした。神様の御業の素晴らしさ!感謝!ハレルヤ!
ひよこじゃないのに!!!!
2015.4.27
ひよこ組(満三才児クラス)からもも組(三歳児クラス)に進級したK君は5歳のお姉ちゃんのマネをして縄跳びを始めました。ところが思うようにというより全く跳べていません。見ているとぶつぶつ何か言ってます。
「ひよこさんじゃないのにできない・・・」と怒っています。K君の考えでは進級して大きいクラスになったら今までできなかったこともできるようになると思っていたようです。
進級して一つ上のクラスになっても、誕生日がきて一つ年をとっても練習をしたり、努力しないと出来ないことがあります。大人にとっては当たり前の事ですが、幼い子たちにはその一つ一つを経験しながら、心と体で覚えていきます。その時に、悔しい気持ちや残念な思いをしながら過ごす時間の大切さ。そしてできるようになった時の嬉しさ。出来ないところから一つ一つ積み上げている子どもたちの姿に私たちは励まされています。
4月16日
2015.4.16
年長組のA君とBちゃんがブロックを高く高く積み上げていました。とうとう自分たちの手では届かないくらいに高くなりました。色々考えて、積み木で踏み台を作りました。
すると高く積みあがったブロックの塔が倒れそうになってます。
今度はブロックが倒れないように他の積み木でガードし始めました。
ただ高く積み上げていたブロックをできるだけ高くするために、様々な障害を二人はとてもよく心と頭を使って乗り越えました。お片付けにはもうその塔はすっかり片付けられていました。でも今日二人が体験した心と頭の働きは経験として残っています。どうしても見える物でなければ判断や評価ができなくなっていますが、子どもたちは園の中で毎日様々なことを体験し、考え、失敗し、成功しています。具体的に見えてこなくても充分に心と体を使って遊んでいること信じてください。
4月10日
2015.4.10
「ママね、泣いてていいって言ったの」ともう泣き止んだT君が笑顔で伝えてくれます。「そうだね。泣いてていいんだよ。でももう泣いてないね」「うん!」と元気に遊びの中に入っていきました。
「ただ、帰りたいだけなの」「そうだよね。帰りたいよね。わかるよ」
今までずっと一緒だったお家の方々と離れて幼稚園という社会を
経験している子どもたち。それぞれに自分のもっている社会性を働かせて少しずつ幼稚園に慣れて行ってます。
進級児は?さすがにお兄さんお姉さんの顔とプライドをもって?泣いている子に担任の手が取られていると、スーッと園長や事務の先生の膝を占めています。幼いながらも空気を読み、今の状況を把握して、ちゃんと自分の居場所を見つけられています。それも社会性、成長の一つですね。
それでも遊びの中頃には自分の遊びを見つけ、相手を見つけて遊んでいる姿があちこちに見受けられます。
ここも安心できるあなたたちの場所。存分に遊んで帰ろうね。
始業日
2015.4.7
”おはよー!” ”おはよー!””おはよー!”
元気に登園してきた子どもたち。担任は毎年変わります。
きっとドキドキ、ワクワク。そして不安も入り混じりながらの新学期。のはずが・・・・
担任が変わっていても、クラスが変わっていてもお構いなしに遊びだした子どもたち。当園は少人数ですから保育者の一人ひとりが、園児一人ひとりとすでに信頼関係をもっています。大好きな人がいるからその場所、環境に慣れる。逆に安心できる大好きな場所だから大丈夫という安心感があって慣れていく。人的環境の大切さ、そして空間的な環境の大切さ。両方の大事さを改めて
感じさせられました。
明日から来る新入園児も早く私たちに慣れ、場所に慣れてほしいと切に願います。ここはあなたが居て良い場所。あなたが守られる場所。あなたが愛される場所。
雨と雪は友達?
2015.1.23
冬休み中すっかりご無沙汰してしまいました。今年もよろしくお願いいたします。
T君が温度計を指さして「これ小さい時計だね!?」と言ったので「これは温度計だよ。暑い、寒いを計るんだよ」の会話から、雨が寒くなって雪に変わること、お母さんの今日のお仕事の事、おばあちゃんの体の事と様々に話が展開していきました。子どもは子どもなりに色々なことを考え、感じています。
その日、その子はお母さんが朝から忙しく、出かけなければならないことを聞いて、少し不安があったようです。でも、身の周りの色々なことを話していくうちに、「大丈夫。今日も元気でここにいる。」ことに安心していきました。話すことは当たり前すぎてあまり重要視しませんが、子どもにとっても、大人にとっても、とても大切なことです。自分が思っていること、感じている
ことを言葉にすること、誰かに聞いてもらうだけで、安心したり、落ち着いたり。話しながら解決の糸口がわかったり、何も状況が変わらなくても、なぜか納得できたり。不思議ですが、大切なことです。
話たいことがあったり、何か腑に落ちないことがあったり、腹立たしいことがあれば、誰かに話してみてください。もし誰にも話せないことや、笑われるかもしれないと思うようなことは私で良ければお聞きしますよ。秘密厳守で!
お楽しみ会
2014.12.19
今日、学期末のお楽しみ会をしました。
クラスの枠を超えてグループを作り、対抗リレーや全員参加の
フルーツバスケット!大きい子は小さい子をかばいながら。
一番大きいクラスの子にはハンデがあって。ぶつかって泣く子も
なく、とてもとても仲良く楽しんでいました。小さいころから様々な関係の中で関わりあうことの大切さを思わせられます。
約束していないから遊べない。同じおもちゃ、ゲームを持っていないと遊べない。知らない子だから遊べない。ではなく、知らなければ知っていきましょう。分からなければ聞きましょう。互いに言葉を交わして、感情を共有して信頼関係を少しずつ築いていけばいいんです。この幼児期にこのような経験をしていくことが必要だと心から思います。
ゲームの後はみんなでホットケーキづくり。今年は1学期から”ぐりとぐら”の絵本の世界を楽しんできました。運動会もそのテーマの中で行いました。今回も、しめくくりはカステラとはいきませんでしたが、ホットケーキを焼いてお昼のデザートに!
お昼は肉じゃがを作って食べました。みんなで同じものを食べることってどうしてこんなに楽しいのでしょう!おいしいのでしょう!
今日は楽しい、おいしい経験をたくさんしたい1日でした。
完成しました
2014.11.27
前回お伝えしたロバの子の共同製作ですが、大きな大きな
ぞうときりんとわにが完成しました。子どもたちが乗ることができるほど大きくて頑丈な物ができました。
何かを作り上げる達成感。友達と頑張った中で生まれた共感。
一つの物を作り上げることで多くのことを学び、吸収していく子どもたち。
ロバの子
2014.11.18
今日はロバの子のグループで牛乳パックを使って共同製作をしました。ひとグループ15人から18人で、3歳児から5歳児までの混合のグループ。
5歳児がリードしながら、”きりん””ぞう””わに”をそれぞれつくりました。1学期からの積み重ねもあってもうみんなクラスが違っても仲良くなっているので、大きい子は小さい子たちに教えたり、言葉がけをします。小さい子たちもどんどんお兄さんお姉さんたちに頼りながら、作業を進めていきます。
子どもたちはそれぞれのやり方で、友達を作り、和を広げ、深めていきます。ストレートにぶつかったり、言葉がきつかったり、言葉が足りなかったり。トラブルになれば涙も出ます。でもその繰り返しの中からそれぞれが自分自身で人との関わりを見出し、信頼していきます。幼児期だからこそ様々な人間関係の中で成長してほしいと思います。