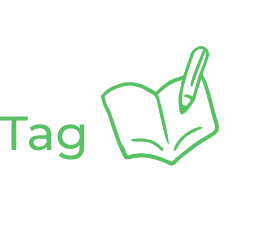行きて帰りし物語Vol.Vol.2
2017.4.18
新学期が始まりました。入園して来たお友達も少しずつ慣れて落ち着いて来ました。進級した子たちもお部屋が変わり、担任が変わり、新しいお友達も加わり新しい環境になじんできました。年少児、年中児が一つ上のクラスになることは本人たちにとっては大人が考えているよりもプレッシャーのようです。大きな期待と嬉しさの反面、今までの年長組さんへの憧れがあればあるほど、そうなりたいという思いから、緊張した様子で登園してきます。
そんな緊張がほどけてくると、ふっと元のお部屋に間違って行ってしまう子が少なくないです。気が付いて慌てて新しいお部屋へと恥ずかしそうに走っていきます。その中で、意識的に?無意識に?元のお部屋へふらっと行く子がいます。嬉しい事もあり、誇らしげに一生懸命進級したクラスで頑張っていますが、ふっと一息つきたいときがあるようです。
前回”行きし帰りし物語”でもかきましたが、実際の生活の中で元の場所へ戻ってみる。お母さんに甘えるだけではなく、元の自分を確かめてそして一歩また踏み出して行く。日常の当たり前の流れの中でも子どもたちは大きな冒険を経験しながら一日を過ごしています。そしてそれは私たち大人にも言える事ではないでしょうか?
マリつき
2017.3.10
昨年の11月くらいから、ボールをつく事に取り組んでいる子がいました。なかなかうまくつく事が出来ずにいました。3回ついたら、足にぶつかって転がったり、何度やっても、何日やってもうまくできずにいました。それぞれに得て不得手があってすぐにうまくできる事、何度もやってみないと出来ない事がありますね。できない事に取り組むのは大人にも困難な事です。
でもついこないだ、その子がとても上手につけるようになっていました。毎日少しずつ諦めずに頑張っていた成果です。遊びの中で子どもたち一人ひとりがそれぞれのやりたい事、乗り越えたい事、克服したい課題に取り組むために、自由な時間と場所が必要です。その保証をしていくのが教育現場でもあると思います。それぞれが自分から主体性をもって取り組む課題。それを達成しようと、日々、様々なかかわりのなかで、自分なりに時間や場所をみつけて取り組めること。そして達成したことはその子の力となり、自信となります。マリつきという些細なことですがその
その積み重ねが土台となり、その子自身が形成されてい来ます。保育の専門性をもって保育者側から提供するもの、そして子どもたちがそれぞれに取り組む時間と空間をしっかりと保障していきたいと考えています。
成 長?
2017.2.16
”行事が一つ終わるごとに子どもたちはそれぞれに成長する。”それはこの仕事について初めての運動会を終えた時に気づき、大きく感動した事でした。その事実は今も裏切られてはいません。
どこが成長しているか?と言えば、子どもたち一人ひとりそれぞれですが、何かが出来るようになったり、今まで以上に多く、高く飛んだり、回ったり。目に見えてわかることもしかりですか、一人ひとりが自信をつけているというのが一番だと思います。どうしても運動神経の良い子やダンスのセンスのある子などが目立ちます。目立たないで、終わる子もいますが、その子たちこそ、心の成長は大きいと思います。何度もやり続ける粘り強さや、失敗した時の悔しさ。そして成功した時の達成感等。
また、大切なのは行事のための準備というより日頃の保育がどう行われているか?です。日々の中でそれぞれが十分に自己表現ができ、周りに認められていることが根底に必要です。
幼児期は特に見えない所の成長が大切です。そこに目を止めていけるよう心がけたいですね。
3学期始まりました
2017.1.30
昨日から3学期が始まりました。今日も全員出席で元気いっぱいの子どもたち!早速今朝は隣のすずらん公園で雪遊びを楽しみました。ウェアーの着脱、靴に雪が入らないようにつけるカバー等、園の集団生活の中では出来るところまでは自分で頑張ってもらいます。最初にしっかり伝える事で何度か助けるだけでちゃんとできルようになります。
今日3学期初めての外遊びでしたが、とてもスムーズに自分たちの支度が出来ていました。ご家庭でも頑張っていることがうかがえました。ありがとうございました。
靴カバーを外して、脱いで、ついてる雪を落として、乾かすためにホールまで持って行くという一連の動作は大人には聞いてすぐに行動に移せても、いつもと違う動きであり、体の小さな子どもたちにはその動作から大変なところもあります。それを一人ひとり、丁寧にお教えていくには忍耐を要します。私もまだまだ未熟ですから、言葉の使い方が乱暴になったり、「早く!」を連発したり…理想の優しい先生像にはほど遠い現実があります。
ドッチボールのようなルールがある遊びを教える時も最初は先生の言葉ばかりが行き交い、ゲームにならない状況ですが、何度か回を重ねるうちに形になって行きます。いつも最初は大変ですね。でも最初を丁寧に伝え、一人ひとりが理解するともう大丈夫。この最初の関わりをしっかりすることで信頼も深まります。ちょっと言葉も荒くなっても、それが子どものためです。
いもの塩煮
2016.9.28
先日収穫したジャガイモをお誕生会に塩煮にしました。大人であれば塩からをのせて食べると最高ですが・・・バターやマヨネーズを用意しようと考えましたが、ジャガイモ本来の味を知ってほしいと思い、あえて塩だけで食べました。ちょっと多くゆですぎたと思ったお芋を子どもたちはあっという間に平らげてしまいました。よほどおいしかったのでしょう。
素材だけで味を楽しめるのは、とても贅沢なことではないでしょうか?様々な調味料でしっかりと調理しなければおいしく食べられないものではなく、ゆでたまま、塩だけで食べられること。ジャガイモに限らず、北海道はおいしいものがたくさんあります。
素材の味を知ることも食育であり、五感の刺激になります。ファストフードやスナック菓子の味で育ってしまいがちな今の子どもたちに、旬の本物の味を知ってもらいたいと切に思います。そのものの味を知ることは、鮮度や傷みなどにも気づけます。身を守ることに通じます。自然のものを食する事の貴重さを改めて考えさせられました。
あいさつ
2016.9.15
「高橋先生 おはようございます。」
私が32年前、勤め始めた時の毎朝の子どもたちとの挨拶でした。私も挨拶はちゃんとしているつもりでしたが、相手の顔を見て、相手の名前を言って挨拶をするのは、自分が認められているようで、とても嬉しい気持ちになりました。挨拶一つで、相手を認めていることが伝わります。そんな小さなことがその人を認め、その人の自信につながります。
運動会で頑張るリレーや跳び箱。出来る力やセンスはもっているのに、なぜか力を出し切れていない子が居ます。「自信がない」体を動かすことの自信ではなく、自分の存在に対する自信。色々なことができているのに、なぜこの子は?何ができたから、何かが上手だから認められるではなく、何もできなくても、失敗
してもその子のその存在がかけがえのない、大切な物である事。その子の名前を呼んで挨拶すること。なんでもない時にも抱きしめて、言葉で「あなたは大切な子」であることを伝えていく事。時々はその子の体にぴったり合ったその子の服が与えられること(普段はおさがりで大丈夫)。誕生日に生まれてきたことを感謝すること。いま在ることを良しとされ、喜ばれることが大切です。そしてお父さん、お母さんご自身も大切な大切な存在であることに自信を持ってください。
自分たちで遊びを
2016.8.5
北海道にしては熱い、湿度の高い日が続いていますね。いかがお過ごしでしょうか?慣れない暑さに体も気持ちも疲れ気味ではないでしょうか?
最近、子どもたち(大人たちも)「〇〇ゴー」というゲームで様々な名所や公園等に出かけているというニュースや情報番組を目にします。このゲームの目的の一つには引きこもってゲーム漬けになっている方々が外へでるきっかけになればという願いもあるようですが・・・
子どもたちにはせっかくの夏休み。外ではゲームではなく、体を動かして遊ぶことや、自然の豊かさ、不思議さに目を向けて心を動かす機会にしてほしいと心から願い求めます。
ゲーム、テーマパークやイベントは企画されたものを与えられて遊ぶものです。いずれ、飽きてしまい、更に面白いものを求めます。そこには企画とお金がかかり、ユーザーは次を待っている状況です。
でもおにごっこやままごとなどはいずれ、飽きますが、そこから自分たちで相違工夫して新しいものを作りだしていける可能性が無限にあります。成長し育っていくためにはこの面白さが生きる力や相手の考えにも気づく力につながっていきます。派手さはありませんが、今育てなければならない大切なものです。どうか、ゲームの楽しさよりも自分たちで遊びを展開させていく楽しさを経験させてあげてください。
?
2016.8.1
子どもたちの喧嘩の仲裁にはいると、どちらが先にたたいたのか?どちらが嘘をついているのか?どちらも嘘をついているのか?それと、どちらも自分の正当性を信じているので、負けられないのか?ちゃんと善悪を見定めて、悪い方にはごめんなさい。何かされた方には赦しを促そうとしまうが、時折、どちらかわからず、困る事があります。それぞれの保護者の方はやはり、自分のお子さんの意見を信じます。それが当然です。でも、子どもも自分の利益のためには頑張ります。
まだまだ未熟な子どもたち。幼い頃には間違いも失敗も日常茶飯事です。正直に言えなかった後悔。自分は悪くないのに一緒に叱られた悔しさ。わかってもらえなかった、悲しさ。様々な感情の経験も理不尽な行為への憤りも幼さい時に経験することはかわいそうですが、必要な事でもあると思います。悔しくて、同じことを人にやり返すのか?自分がされて嫌だったことは人にはしないようにするのか?様々な思いのそばに共に寄り添い、感情の行き場所を共に考えていきたいと思います。
育児相談会がありました。
2016.7.14
今日は予定しておりました、育児相談会がありました。講師の藤田春義先生からあらかじめ皆さんから出された悩みや相談から答えていただきました。今まさに乳幼児から小学生までのお子さんの子育て真っ最中のお母さん、お父さんがいらしてくださいました。子育て中はゆっくり本を読むことも、育児相談をすることさえ、目の前の事が大変で後回しになりがちです。それでも、講師の話に熱心に耳を傾けていました。
お話の中に藤田先生ご自身7人のお子さんのお父さんで、必ず1対1のデート、旅行をした話をしてくださいました。日本の家庭にはあまりなじみのない習慣ですが、忙しい子育ての毎日の中、どうしても平等に子どもたちと関わろうとしがちですが、同じことを同じようにすることだけが平等ではありません。それぞれの子とそれぞれに時間を楽しむ事が大切ですというお話でした。
これからもこのような時間を計画しようと考えています。
僕、読めるよ!
2016.7.12
「僕この絵本読めるよ!」と4歳のA君が得意そうに”かにむかし”の絵本を嬉しそうに持ってきました。毎日A君には朝の早い時間に何冊も絵本を読んでいたので、え?読めるようになったの?と驚いていると「字は読めないよ」と言って絵本の絵を丁寧に読み進めてました。
絵本は字を読めるようになるためのものでも、上手に読めるようになるためのものでもなく、子どもがその絵が物語っているものを目と心と体で読み取っていくもので。字を読みながら見ていくも良し。絵だけで読み取っていくのも良し。そして誰かに読んでもらえれば更に良し!
子どもは誰かに読んでもらった絵本の世界を今度は自分なりに展開していきます。読んでもらったお話しを頭の中で考えながら、想像を広げて行きます。その想像や広がりは無限です。じっくりと絵本を見入っている横でその楽しそうな、思いに共感できればと思い寄り添って見たりして・・・