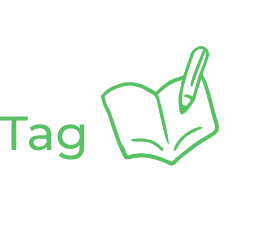少年犯罪
2018.6.15
毎日のように残虐な犯罪が報道されています。インターネットで知り合った者たちが殺人や自殺を計画したり。殺人などの凶悪犯罪が低年齢化してきています。その犯罪を防ぐために極刑や刑罰を重くすることを望む声も大きく取り上げられています。
犯罪に対しての刑罰は必要です。でも、できれば犯罪者にならない育て方、教育を切に願い研究したいと考えます。犯罪者たちを調べていると、ほとんどの方々に「愛着障がい」が見られるとあります。愛着障がいとは母親をはじめとする養育者に愛情
深い関係が何らかの理由(虐待、死別等)で形成されず、情緒や対人関係に問題があ
ることです。家族の中で普通に育つことが困難な時代になってきたのでしょうか?今目の前にいる子どもたち、家族と優しく労りあい、時にはけんかやもめごとがありながらも、共に暮らしていく。その普通の生活が当たり前ではない幸せと感じること?愛は教育しないと育たないとある大学教授がお話ししていました。愛の教育はまず、家庭の中にあります。いつくしんで子どもたちを育てていくこと。この当たり前のことが守られていくことを願い、また、お手伝いしたいと切望しています。
1人ひとりの子どもたち
2018.6.14
「Aちゃんもこっちに来て遊ぼう」
「今絵本読んでる!」
Bちゃんが一人でいるAちゃんを気遣い、声をかけていました。Aちゃんは眼にいっぱい涙をためて、Bちゃんの方も見ず、絵本を見ています。きっとAちゃん、Bちゃんを含めた数人の女の子の中で何かあったようでした。
BちゃんにはA ちゃんは今絵本を見たいから大丈夫だよ。誘ってくれてありがとうと伝え、遊びに戻りように勧めました。Aちゃんの隣に座り、顔を覗き込むと、絵本の中のお話をしてくれました。涙は少し消えていました。
そして、誰かに何かされた、何か言われたと訴えることなく、いつものAちゃんに戻っていきました。子どもたちの世界はそれぞれがまだまだ未熟です。3歳くらいの頃は周りの大人に助けを求めることで解決しましたが、4歳、5歳にもなると、友達との関わりの中で、お互いの言い分があり、ある程度、わがままや、我慢する必要を覚えていく中、自分たちで納めていけるようになります。
一人ひとりの子どもたちの心の動き、成長に寄り添い、見守っていきたいと考えています。
絵本
2017.12.5
絵本は子どもたちが字を読めるようになったら自分で読ませるようにしますが、絵本は読み聞かせるもの。読んでもらうものです。
朝、泣きながら登園してきた子に、その子の好きな絵本を読みました。
1回目。2回目と読んでいくと自分の好きなところにくるとふっと泣きやみます。3回目になると、すっかり機嫌もなおり、遊び始めました。私たちもそうですが、落ち込んだり元気がない時に、物語や、好きな歌などの自分の好きな、元気をもらえる場面や言葉などに力をもらい、気持ちを立て直す時があります。
絵本は心に元気を与える力があります。また、読んでくれた人のぬくもりや声の暖かさ。その時の空気感まで思いだし、自分が愛されていること、大切にされていることを心と体で思いだします。
そしてその経験を今度は小さい友達に伝えていきます。たどたどしい読み方ですが、小さい子たちは黙って聞いています。そんな関係と時間と空間を守っていくことの大切さを日々思わせられます。
ごっこ遊びから
2017.10.13
FBにもあげました。日々の保育の中でそれぞれのクラスが取り組んでいる遊び。年少組はキャンプごっこ。年中組は1学期から続いている”カラスのパン屋さん”から森づくりに取り組んでいました。それが今朝、森でキャンプすることになりました。そこから出てくる子どもたちの発想。「川があるといいね」
「魚釣りがしたい」「橋を作ろう!」「釣竿作ろう!」と子どもたちのイメージはどんどん膨らんでいきました。保育者はその思いをできるだけ実現できるように釣竿や魚の材料となるような素材を用意して考え、作り、遊びこむ。見ているこちらもわくわくするような遊びの展開となっていました。もちろん要所要所でリードしてくれたのは年長組。さすがに一歩先を心得ていました。
年少、年中、年長が自然に意見を出し合い、助け合い遊びを展開しています。子ども自身が自分で考えイメージしたものを実現していくこと。それはどんなに多くの知識を詰め込むよりも、成長していく段階でその子自身の力となり、勇気となり、自信につながります。これが自己肯定感を育んでいきます。
運動会後のあそび
2017.9.26
今年度は”かおりフェスティバル”のテーマで運動会を楽しみました。当日は晴天に恵まれ、気温も暑からず、寒からず。申し分のない状況でした。
行事を一つ終えると子どもたちは内面的に一つ成長します。自信が着き、周りのことが今までよりも見えるようになっていると感じます。
跳び箱をさらに飛べるように取り組む子。年長さんの競技を見て今まで興味がなかった縄跳びに挑戦している年中さん。
競技のために作った大道具を使ってままごとに発展させているこどもたち。ゆったりと流れる時間の中でそれぞれが挑戦してみようと思うこと。やってみたいと思う思いをそのまま実現させてあげること。それぞれの子供たちの思いを展開、実現させてあげるにはわたくしたち保育者の資質にもかかわることで。十分対応できるように私たちも日々、研鑽を重ねていきたいと思います。
できるかな?
2017.9.22
朝年少のmちゃんが登り棒を登り始めました。年長のお兄さんたちと同じことがしたくて。でも、筋力や体力からみてmちゃんが上まで登るのは無理かなあ?とみていました。
園では自力で登れるところまで登って自力で降りてくるようにしています。手を貸してあげればどこまででも登れます。でも、自分の力量をよく理解してけがや事故から自分を守るために幼いころから学んでほしいと思います。
mちゃんもどうするかな?とみていると、ちゃんと自分が登れるところまで行って、自力で降りてきました。小さいころからの教えはちゃんと見につくものだと感心しました。自分を守ることは周りをも守れることになります。お互いの大切さを覚えながら成長してほしいと願っています。
ある研修会で
2017.8.1
夏休みと言っても様々な多くの研修会があります。
ある研修のある講師がおっしゃっていた言葉です。
「幼児期に投資をしておくと大きくなってからの効果が出やすい」
「3・4歳児で保育を受けると大人になってから優位な仕事につける」
優位な仕事に就き、年収が多くもらえるのは結果であり、いかに幼児期の教育が人間にとって大切か?という事です。お金や地位は後からついて来るもので、幼児期に人として向き合い、豊かな人間関係を経験し、様々な体験をしていくことで、その子が人間性豊かに育ち、与えられたものだけではなく、自らも環境や人間関係を創り出していけるようになる。
どんな状況でも(年収や地位を問題にしなくても)豊かに、健やかに生きて行けることが一番の幸せだと思います。
そして家族の仲の良さも人間形成においてはとても大切な事です。夏休み期間、いつもと違った事、旅行や夏祭り等の中で家族の楽しい、ホットする経験を子どもだけでなく、大人も十分楽しめると良居ですね。
三浦綾子さんのカレンダーから2
2017.7.12
今月の三浦綾子さんのカレンダーの文章は
「土にまいた水が直ちに乾いてしまったとしても、その水が・・・」
その水が土地を潤したことだけはまちがいなく事実である。
毎日毎日読む本が、何の役にも立たないようでも、知らぬ間に地下水のように心の底を潤すものになるのである。
三浦綾子著 「わが青春に出会った本」より
学生時代に学んだこと。幼い頃からの育った環境。出会った方々。多くの友達。先生たちなど。私たちはそれぞれが多くの環境のなかで育ち成長していきます。自分の土台や、感性、情緒。自分自身が周りの環境の中で形作られてきています。そして、様々な本。自分では体験できない事に触れ、自分にはない様々な感情に触れ、さらに視野を広げ、心の深い所に気づかされる。本を読むことは自分を育てるためにとても大事なことだと思います。何気ない、軽いなあと思う本でも、三浦綾子さんの言葉を借りると知らぬ間に心を潤すものになっているようなので、更に多くの色々な本と出合っていきたいと思います。
おもてなし
2017.6.11
東京オリンピックの招致の時に何度となく語られ、今もその思いをもって準備?されていると思います。
私はおもてなしをするのが好きです。誰かが来る時にはご飯を出す時は相手が何が好きか?今の体調がどうか?時間の余裕はどうか?お年はどうか?様々に考えます。来られた方が喜んで下さることが何よりもうれしい事です。
そして逆に自分がもてなされた時に、どれだけ心を尽くして準備したことが伺えること、そこに気づくことも大切な事であると感じます。これだけやってあげたから!と恩を着せるつもりはありませんし、そのような思いがあるのでは最初からおもてなししてはいけないと思います。
大した準備ができない時もあります。掃除が行き届かず、ごはんも買い合わせたものであったとしても来ていただいたことを心から喜んで受け止めることが一番大事ですよね。
毎日子どもたちを園に迎え、どれだけ喜び楽しんで過ごしてくれたか?悔しい思いや嫌な思いもしながら、その全てをこれからの成長の土台にして。その成長を助け、働きかけ、私たちもしっかりと向き合い、心を込めてなすべきことをなして
行きたいと思います。
ひとこと
2017.5.1
三浦綾子さんの本の言葉でできているカレンダーがあります。
「自分一人ぐらいと思ってはいけない。
その一人ぐらいと思っている自分に、たくさんの人がかかわっている。」
三浦綾子著 『人間の原点』
説明に「ある人がでたらめに生きるとその人間の一生に出会う
すべての人が不快になったり、迷惑をこうむったりするのだ。そして不幸にもなるのだ。」とありました。なるほど、私たちはやはり一人では生きていません。必ず何かしらの影響を与えてしまいますし、受けます。
私は説明を読む前にこの言葉を違う意味にとらえていました。
「自分一人ぐらいいなくなっても何も変わらない。誰も悲しまない。なんて思わないで。その一人には必ずたくさんの人がかかわり、その存在を大切に、必要に思っている人がいるよ。」と。
言葉というのは不思議です。奥が深いです。同じ言葉でも様々な取り方が出来ます。同じ人でも時が変われば、違う意味で響いたりします。言葉はひとを励まし、勇気づけもしますが、傷つけ、落ち込ませもします。褒められて成長する子もいれば、叱られて大きくなる子もいます。どのような言葉を発するにも大切に使いたいと思います。