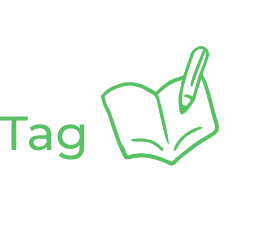どっちにする?
2019.6.4
何かを選ぶときに選べない人がいます。今日着ていく服や、どのケーキを食べるか等を決めるのはそれほど後々に大きな影響はありません。でも、日々の中で、家族の健康に関わる事や、将来に影響する判断もあります。前にも書きましたが、毎日の中での何げない小さな決断が大きな決断をする訓練になります。そして子供は親がどんな判断をしているかを見ながら成長して行きます。でも、今は選択する力量や知恵がないうちに子どもたちに多くのことを選ばせているような気がします。朝、子どもの様子を見て園を休ませるかどうか?子供に聞いて判断する保護者がいると何かで読みました。保護者のかたがたにも今からでも遅くありません。判断には責任が伴いますから、そこを避けたい方々が多数であることはよくわかります。でも、お子さんたちが人生を豊かに生きていくためには様々な多くの判断が必要です。その判断ができるように育てていくには今この幼児期の小さな判断の積み重ねです。そしてそれはまだまだ間違ってもいいのです。間違ったらまた、やり直せばいいのです。保護者が判断するところや間違ってもやり直して前に進むところを見せていくことで、子どもたちも失敗を恐れずに進んでいける子に育っていきます。失敗をしてもまた、そこから違う方法で進んでいけます。どうか大いに間違ってください。そしてやり直すことは恥ずかしくないことをお子さんたちにちゃんと伝えてください。それが家庭の教育力です。応援しています。大事なのは間違えることなく成功することよりも間違えた時にやり直すことができることです。
空想のおはなし
2019.5.8
私 「おはよう」
A君「今日ね。夢見たんだよ」
私 「どんな夢見たの?」
A君「怪獣出てきたの」
私 「怪獣怖かった?」
A君「怪獣仲良しだった」
私 「何して遊んだの?」
A君「ブロックで消防車作ったの」
B君「僕もね、僕もね夢見たよ。」
私 「誰出てきたの?」
B君「アンパンマンとばいきんまん」
と満3歳の男の子二人と私の朝の会話です。この後もお話はどんどん膨らんでいきました。夢をどれだけリアルに覚えているのかはわかりませんが、聞かれたことに様々に考えて答えてくれました。もう一人の子もその会話に入りたくてちゃんと話の中に入ってきました。うその作り話としてしまうのではなく、昨今想像力の低下が心配されている中、満3歳の子にはこんなに想像力が豊かにあります。これを更に豊かに育てていくことが私たちの大切な責務です。お子さんたちと想像を膨らませられるお話しをたくさんしましょう。その中で現実との違いも分かっていきます。満3歳児の時にはちゃんと想像力が備わっています。これを日々の何気ない会話の中で育てていきましょう。
灰色からの手紙
2019.2.6
“灰色からの手紙”という絵の具のセットを既成のもので済ませるか、あるものと手作りのものでそろえるか?を考えるエッセイが載ってました。私は小学校の習字の道具を思い出しました。私の時代はそんなにセットとして数多く既製品があったわけではありませんがクラスの半分くらいは既製品のセットでした。私は叔父たちが使った硯のお古と家にあったカバン。さすがに筆は買ってもらいました。その中で硯の袋を汚れてもいいように使い古したタオルで袋を母が手作りしてくれていました。もしかすると見た目はみすぼらしく見えたかもしれませんが私にとってはとても嬉しい、母の心使いでした。みんなと一緒じゃなくてもいい。誰かのおさがりでもいい。そこに見た目だけではない思いを認められるようになっていたいと思います。
今は作るよりも安くて便利なものがあふれています。時間をかけるよりもお金で解決できるほうを選んでしまう空気があるように思えます。その中で、教育、子育てだけは手をかけ、時間をかけることを惜しんではいけないと思います。コンビニですぐに手に入る卵焼き。少し焦げ目のついた不格好なお母さん手作りの卵焼き。心と体が豊かに育つのはどちらでしょう?忙しい時に何度かコンビニ弁当、カップ麺に頼ってもいいと思います。ただ、それを習慣にしないように気を付けたいものです。お母さんの手作り卵焼きは幼児期の心も育てます。
庭しんぶん 第一こどものとも社監修2月号のエッセイの感想です。
子どもたちを守る?って
2019.2.5
悲しいことに虐待で命を失われてしまう子どもたちのニュースが後を絶ちません。
可哀そうを通り越して怒りでいっぱいになるような周りの対応。今回の千葉の心愛ちゃん。SOSのサインは十分すぎるほど出ていて、保護もしていて、把握していたにも関わらず、尊い命が失われる事態になっていること。あまりにも子どもたちにかかわる大人たちの認識、知識、思いが足りなさ過ぎると感じてしまいます。脅してくる親の元にいる子がどんなに怖い思いをしているか?脅された教育委員会の方は直にわかったのであればそれだけで保護をする理由になるのではないでしょうか?
また、DVの方々はそれだけでカウンセリングの必要を覚えます。子どもを保護しただけで、期間を置いて収まったから返すのではなく、親のほうにこそ徹底した治療と指導が必要だと強く感じます。
その子自身の命、心、情緒が傷つけられることなく成長していくためには、大人の私たちが考え、備えていかなければならないことは多くありますが、行政の規則や様々な壁を乗り越えて守っていくことはできないのでしょうか?本当に心から切に願います。家族に虐待される苦しいつらい日々を過ごしている子たちが今日もいることを覚えつつ・・・失われる命がなくなるように!
かくれんぼ
2019.1.23
「もーいーかーい」「まあだだよー」「もーいーかーい」「もーいーよー」
満3歳児のかくれんぼ。まだまだルールが理解できない、ルールがあることさえもわからない。自分のやりたいこと、自分が良いと思えればそれでいいと考えている幼児に、鬼の意味、隠れること、見つかったら次に鬼になることなどは何度も同じように遊びながら、覚えていくことです。最初は「もーいいかい」の答えに「もーいいかーい」と返し。かわいいのは自分が目をつぶったら見えないので、そのまま自分が隠れられていると信じ目をつぶり、じっとしゃがんでいる子。とても愛らしく、見つけてもそのまま見続けていたいと思うほど。子どもたちが遊びの中でまず、ルールを覚える前に友達や先生たちと楽しく遊びこみ、見よう見まねで覚えていく所、自分たちなりに約束を作って遊び、理解できるようになっていく中でルールがあった方が楽しく遊べることを学んでいく。また、楽しく遊べるためにどうすれば良いか友達の間で約束事を作っていくことの経験がとても大切です。子どもたちが想像を膨らませ、遊びを自分たちで展開させていくことが幼児期にはとても重要です。そしてそれが一番楽しい遊びにもなります。
キリスト教保育
2019.1.22
「ここでこの本読んでいい?この絵本大好きなんだ」と年長のIちゃんが職員室に来て、
ソファーに座りました。たどたどしく声を出して読んでいる絵本は「十字架への道」です。
聖書に書かれているイエスキリストの十字架の場面の絵本でした。絵本とはいっても内容は幼児期の子には難しいものです。「どうしてイエス様は死んだの?」と聞くIちゃん。「みんなの罪のために十字架にかかられたんだよ。でも死んだままではなくよみがえられたんだよ」
罪、死、よみがえり。どの言葉も幼児には難しくすぐには理解できないものです。でもその子の「この絵本好きなの」と持ってきた背景には絵本の正確な内容というよりも、いつも聞いているイエス様のお話。そこには愛があふれ、暖かな空気を感じている。当園は祈りで始まり祈りで終わります。自分の力以外に支えてくれるものがあることを感性でとらえていく中、内容はわからなくても、心には落ち着くところがあるのだと感じます。
幼児教育は何かを教え込んだり、何かができるまで訓練することよりも、自分が受け止め支えられている。失敗してもできないことがあっても存在していていい。その子自身の存在が尊いのだということを心と体でしっかり感じ取っていくことが大事で
す。キリスト教保育はまさにその一人ひとりの存在を認めていく保育です。
クリスマス Ⅱ
2018.12.21
今朝の礼拝の中で子どもたちに「クリスマスはどうして嬉しいの?」と聞いてみました。「プレゼントもらえるから」「サンタさんくるから」そして「イエス様が十字架にかかってくれるために生まれた誕生日だから」と今までの習慣であった楽しさと、クリスマスの本当の意味を礼拝の中で聞いていた子たちの素直な答えが返ってきました。
小さな子どもたちにとってはまだまだプレゼントをもらう側。ツリーの下に置かれたプレゼント。目を覚ましたら枕もとに置かれているプレゼント。
わくわくドキドキします。期待の中にある子どもたち。その子たちに今日はもう一つ。「もらうだけではなく、みんなにもできることをしてみようか?」
ということで、いつも守ってくれている保護者の方々へ、日々の感謝を伝えることはとても大切で、お母さんお父さんにとっては感謝されることはとても嬉しいことであることを伝えました。クリスマスはどうしてもサンタさんやケーキやごちそう。プレゼント交換などがメインになりますが、お互いに感謝しあうことが何よりの喜びだと考えます。もうすでに神様がイエス様を私たちのために与えてくださったのですから。思い通りにいかないこともまだまだ目の前に課題としてあるかもしれません。でも、今、在ることだけで、感謝であることに気づけることが大事ではないでしょうか?
今年は9月に大きな地震がありました。そのことで子どもたちも私たちも多くのことを学び、今までとは違う思いで日常を送っています。そして普通に送っているこの日常が当たり前ではない特別な祝福であることをもっともっと深く知ることが出来ました。
今年の特別なクリスマス。誰にどんな感謝を伝えますか?
尊さ
2018.10.4
「生産性がない」という言葉を議員さんがおっしゃって話題になっています。人として生活している私たちに生産性という言葉を当てはめること自体が私には疑問です。人はそれぞれの個性があり、どんな人でも計画をもって生まれてきました。何のために創られ、生かされているかを知らない方々の考える方向は相手を傷つけることを自分の踏み台にするような発言もさせてしまう。目に見える利益や功績、手柄が無ければ価値が無いという考え方は、何十年も前の身分の低いものの人権が認められていない、時と同じ後退した考え方だと思います。キリスト教保育はそれぞれ、一人ひとり、かけがえのない尊い存在であることをこの幼児期に心に刻んでいく保育です。何かが出来たから、価値があるのではなく、何もできない、失敗だらけであってもの、その存在そのものが大切なものであること。利益を求め、その存在に何か価値が無ければ虐げられるのは人として共に生きていくうえで、最も最低な考えだと思います。子どもたちがこの幼児期に自分の存在の尊さ。そして友達の存在の尊さをしっかりと心と体に覚えて育ってほしいと願っています。ですから、その子らしさ、自分らしさをそのままの形で、自信をもって生きていってほしいと思います。また、そうするために保護者の皆様も自分自身に自信をもって子どもたちと関わってください。その自信の根拠はただただ、その子の保護者であるということで十分です。
良い事?
2018.8.24
子どもが車道に飛び出しそうに駆け出したので、「走っちゃだめ!」
ととっさに大きな声を出したことがありました。近くにお母さんがいて、
「ほら、怒られたじゃない!」
Aちゃんがお友達を叱っていました。「そんなことしたら先生に怒られるよ!」
あれ?それはちょっと違うなあ。誰かに怒られるという基準で良い事と、悪いことを決めているのは違います。子どもが成長していく時に様々なことを学び、身に着けていきます。善悪の判断がその子の良心にしっかりとした基準で身につけてほしいと願います。人は悲しいことに悪い言葉、ずるい事、うそは誰に教えられなくても身についていきます。その時に正しく道を整えていくためにも大人の役割は重いものがあります。と書きながら自分自身もそこに立てるように。吟味しながら。失敗しつつも、あきらめないでいきましょう。
ブロック遊び
2018.6.22
5歳のA君は1番バスで到着し、大好きなブロックで遊び始めました。
まだ子どもたちがそろっていないので、たくさんのブロックを使っています。
そこへ4歳のB君たちが来てそのブロックを貸してと言いますが、貸してあげません。何日か続いた中で、「A君、小さい子たちもこのブロック使いたいんだよ。貸してあげられるとみんなも楽しんで遊べるんだけどなあ」と言ってそこを離れ、少したって行ってみるとA君は全部のブロックを他の子に貸していました。そのことを「すごいねー。A君!さすが!お兄さんだね!」
と褒めると、ブロックを全部貸してしまってちょっと後悔していたA君の心は褒められたことの方が嬉しくて、次の遊びの中でどんどんお友達と積極的に遊びを展開していました。
友達の分まで使って自分の好きなように遊んでいるときよりも、少し我慢ができたこと、認められたことが自信となっていったのだと思います。全てがそろって自分の好きなようにできるより、不足の中で、我慢すること、相手を思いやることを学び、大人になっていくことの方が、嬉しいものであること。A君は今日大切なことを得ることが出来ました。