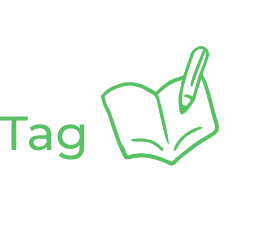バイバーーーイ‼‼
2020.2.19
バイバーイ!また明日ね!
バイバーーーイ!バイバーーーイ!バイバーーーイ!
降園時、玄関でバスに乗る子、お迎えの子、預かりの子と何度も何度もバイバイを繰り返し、さよならをしながら、別れを惜しんでいる子どもたち。その声を聴きながら、それぞれの友達との1日がどんなにか楽しかったのかということが伝わってきます。どんな遊びをしたのか?誰と遊んだのか?様々な子どもたちのそれぞれの1日1日が平和で楽しく過ごせたことは何と幸いなことでしょう!保育者として、その子が喜んで帰れることが一番の幸せに感じる時です。今日も1人ひとりの子どもたちが十分に楽しみ、喜んで遊びこんだ1日がおくれるよう、すべての環境を整えていきたいと思います。
みんな大好き会
2020.2.12
2月15日は「みんな大好き会」(発表会)です。この1年保育の中で取り組んできたことや遊びこんだことを発表するために、劇遊びにしたり、お遊戯にしたり子どもたちと保育者が試行錯誤して取り組んできました。でも、日々の保育を目に見える形で表現するのはとても難しい作業です。
この時期の子どもたちはそれぞれの個性の違い、成長のスピードもアンバランス。そして月齢の違いは体格にも現れています。まだまだ未開発のこどもたち。苦手なことや嫌いなことにも頑張ろうとする思いを育てるのもこの時期です。他のお子さんと比べての成長ではなく、今目の前にいるお子さんの成長を焦らずにゆっくり見守っていきましょう。
家族
2020.1.30
先日、お母さん方と話している中に「家族との時間を大切にしたい」という話題がありました。小学校に行って、スポーツクラブに入ったり、習い事をすることで、今までの生活リズムが変化します。お母さんが自分のスキルを活かして仕事を始めても、預かり保育の利用や、帰りの時間などで変わっていきます。今この時にその仕事や、習い事が必要であれば考えなければなりませんが、幼児期のお子さんにとっての家族との関りはこの時にしかはぐくめない人としての信頼関係の土台造りであり、愛着の関係を養う大切な時期です。家族での時間を大切にすることの評価は今すぐに見えてくることではありませんが、これから、成長していくための大切な時間と空間です。お仕事を持たれてお忙しい保護者の方々には大変だと思いますが、少しでもお子さんたちとの時間を共有することをおすすめします。
家族との時間を大切にすることを優先したことを話されていたお母さんたちの判断が間違いでなかったことが必ず、実を結ぶはずです。
お弁当箱
2019.12.19
今は給食を行う園が多くなってきました。働くお母さま方、様々なご事情がある方々のために、今はとても必要になってきました。
自分が教諭になった頃、研修の中でお母さんたちは「かえって来たお子さんのお弁当を開けただけでその日のお子さんの様子を読み取ります」とお話ししていました。給食になるとそこが見えにくくなりますが、きっとそれぞれのお子さんのサインがあるはずです。日頃の日常のお子さんをよく見ていれば、必ずわかってくるはずです。
なんでもインターネットを調べれば数秒で回答が出てきますが、お子さんの心の状態、体調はそば近くでにいる保護者の方でなければわかりません。お子さんと関わる時がいつも大切にできるとよいですね。
固まってていいよ
2019.11.22
5歳のR君がお母さんに「お母さん。固まってていいよ。」と言ってくれたことを聞きました。
主婦の皆さんは朝から夜寝るまで、食事の事、家族の着ていくもの、持ち物の事、洗濯、明日の用意等、多岐にわたって準備し、予定を確かめてお子さんやご主人の1日1日が平和に過ごせるよう、配慮しています。きっとお子さんの前でも、忙しく、気配りをしながら、動き回っている姿があるのでしょう。
そして乳幼児はできるだけ母親が自分の方に向いていてほしくて、要求してきます。用事がなくても何か作って自分の方に向けようとします。そこで信頼関係を築いているので、それも大切なことでもあります。でも、R君はお母さんに対して、「固まってていいよ」と言えました。お母さん、今は何もしなくていいよ。お母さんの時間にしていいよ。という意味で言ってくれたというのです。大きく一つ成長したと感心しました。自律の一歩ですね。
そして、もう一つ。忙しい生活の中で、ふと、立ち止まるときがどんなに大切なことか。次へ次へと仕事をこなしていく流れを一度ストップさせて、周りを、自分を見つめてみること。そんなに急ぐ必要はなく、明日のことは明日心配すればよいこともたくさんあって。自分の心に向き合う時間をゆっくりとる事。固まる時間を私も作っていこうと思います。R君ありがとう。
忘れ物
2019.10.18
よく、忘れ物検査などをして忘れ物をしない意識を高めたり、時間割をなんども確認する習慣を付けたり。保護者が低学年のうちはしっかり見てあげたり。でも、今の忙しい社会においては、保護者の方々も子どもたちの準備に対してままならないところがあるようです。忘れ物をしないことは大事なことですが、幼児期、小学校の低学年のうちの忘れ物は取り返しがつくものです。取り返しがつくうちに何度か、忘れ物やほかの失敗をすること。そしてその失敗をどう乗り越えるか?というを経験して育ってほしいと思います。忘れ物をしたとき、失敗したときの思いは皆さんも経験があると思います。それぞれに感じ方は違いますが、自分が我慢しなければならないことや、周りに迷惑をかけたことへの申し訳なさ、どうやったら取り戻せるか?考えること。失敗には非認知能力をフルに使わなければならない面が多々あります。あえて、忘れ物をする必要はありませんが、子どもたちが自分で準備して、いくつかの不足があった時に全てを周りが整えるのではなく、失敗する経験をすることが大切です。そこから学ぶこと、成長することがたくさんあります。失敗する恥ずかしさを乗り越えながら、人は大きくなります。マニュアルでしか考え、行動できない大人に育てるのではなく、子どもたちには予想外のことが起こった時に目の前にある状況から、打開策をみつけ、進んでいけるよう、クリエイティブに育ってほしいと切に願います。
先生、あのね
2019.10.3
「せんせい、あのね、この靴下おかあさんに買ってもらったの。」
「せんせい、あのね、今日ばあばとプール行くの。お兄ちゃんとおねえちゃんも。」
「せんせい、あのね、これ虫なの。でね、魚になっちゃうんだよ。そしてね」
満3歳の子との会話です。向き合ってゆっくりじっくりきいていると、延々続きます。お話はとりとめもなく、本当の出来事とそうでないものとが混ぜ混ぜになっていますが、楽しそうにたくさん話してくれました。
聞きながら、この時期の子たちはこうして自分の話を聞いてもらいながら、自分の存在を確かめているんだなあと感じました。この子にとってこの記憶はきっとひとかけらも残らず消えてしまいます。でも、受け止めてもらったことは魂、情緒が受け止めます。乳幼児期の大切なところはここだと思います。何気ないまいにちですが、その中で普通の事。朝起きてごはんがあって、洗濯されたものを着て、遊び、1日を過ごす。周りに自分をまもり、育んでくれる方々がいてくれる。その日々の中で健全に心身は成長していきます。その積み重ねを通してお子さんたちは自分が保護者の方々に愛され、存在していていい、大切な者だと自己肯定していきます。今の、今しかない乳幼児期をできるだけゆっくり向き合う時間をとり、楽しんでください。私たちも微力ですがお手伝いさせていただきます。
夏休み
2019.7.25
夏休みの季節ですね。私の小中学校時代は周りには両親共働きの方はあまりいませんでした。(すみません。50年近くも前のことです。)長い夏休み。朝から晩まで遊んだ思い。そして時間を持て余した思い。退屈ではあったけれど、その中でいろいろなことを考えたり、試行錯誤して時間をつぶしたり…今思えば貴重な時間だったのではないかと思います。幼稚園で預かり保育、学童保育をしながら、できるだけ、ゆったりと家庭にいるように過ごさせてあげたいと思いつつ、人数が多いとそれだけでも確保してあげるのが難しい状況があります。
低年齢の子にはスキンシップの大切さが言われますが、小学生にも言えると思います。実際にハグをしたり、触ったりしなくても、帰宅したときに今日あった出来事を聞いたり、一緒にいる時間を特別に持つこと等。中学生になったら、さらに何を考え、何を感じているのかを何時も気にかけていることを家族の方々は伝え続けていくことが大事だと思います。日頃お忙しい日々をお過ごしの方々が多くなり、子どもが夏休みになってもお仕事はそうはいかなく、時間が取れないかもしれませんが、お子さんと向き合う時間をこの夏大切にしてみてはいかがでしょう。
朝の子どもたち
2019.6.12
「おはよう‼」と元気に登園する子。
なかなか挨拶ができない子。
小さな声で「おはよう」とようやく絞り出せる子。
それぞれにその表情は毎日違います。保護者のかたがたと離れて、「今日何して遊ぶ⁉」と意気込む子もいれば、保育者の膝の上でしばらくゆっくりと周りの様子を見る子。保護者が仕事に行ってしまったさみしさをどうおさめようか?時間がかかる子。保育者は登園してきた一人ひとりの様々な思い、様々な感情思に寄り添えるよう努力します。
とてもとても忙しくなってしまった、今の社会の中で懸命に働かれている保護者の皆さん。毎日お疲れ様です。もっと子どもたちと向き合いたい。もっとゆっくり一緒にご飯が食べたい。お風呂に入りたいという思いがありつつも、許されない現状があります。忙しい時間に預かってもらうだけでは子どもは安心して成長できないと思います。その時々の思いを受け止めてくれる誰かがそばに居なくてはと。保育者として子どもの隣に寄り添う者として十分とは言えませんがそれぞれに子どもたちの思いを受け止めつつ、平和に安心した1日を子どもたち一人一人が過ごせるように!願っています。
今目の前の子に!
2019.6.7
幼い命が失われる事件、悲しい親子殺人が毎日のように報道され、心痛める日々が続いています。虐待をする親たち、引きこもりの息子を心配して殺人をおこした父親。多くの方々を傷つけて自死してしまった方。殺人を犯した方にはやはり、”愛着障がい”が見え隠れしています。乳幼児期に愛情をもって育てられることの必要性です。今、ニュースで報道されていることは10年20年前に防ごうと思えばふさげたことでもあります。ということは、今、目の前にいるお子さんたちをとにかくかわいがって育ててください。乳幼児期だけではありません。小学校に行っても中学生でも話したいことをすぐに話せる親がいつもそばにいてくれることが大切です。お仕事をもっている保護者のかたがたには忙しさの中で難しい所ではありますが、できるだけ、今向き合うときは向き合い、話さなくてもそばにいてくれている。自分を見ていてくれるという信頼を築くことです。後悔をしないためではなく、親子、家族の関係はこの信頼関係があってこそです。今この時期はもうきません。今を大切にしましょう。