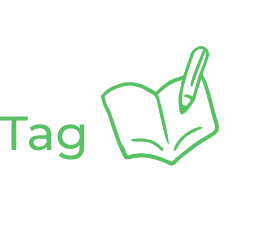絵本の世界
2015.9.17
Sちゃんが「先生、これ読んで!」と持ってきたのは”三びきのやぎのがらがらどん”私も大好きな絵本なので、感情を入れながら、楽しみながら読みました。小さいやぎや二番目のヤギがトロルに会う時は絵本のヤギをトロルから隠すように手で覆いをつくるSちゃん。大きいヤギとトロルの戦いになると絵本から距離をとって遠巻きにのぞいています。
絵本の中にすっかり入りこんで、それぞれのヤギたちと同じ思いになって恐がったり、ホッとしたり・・・
絵本の中から様々な状況を読み取り、色々な感情に出会います。間接的ではありますが、多くの直接には出会えない、感情や状況に出会います。その経験を通して人の痛みや、淋しさや、戦争の悲惨さ等。幼くても受け止められる範囲で様々な事に触れていくのは、大切なことです。
トロルに会うことは実生活ではありえない?ことではありますが、絵本の世界に入り込み、その世界を思う存分楽しみ、感情を豊かにし、動かない絵を見て、想像力を育てていく。お話の続きが気になって、終わってしまった物語に自分でお話をつくった。幼児期にはとても大切な作業です。未だに私はお話の続きを自分なりにつくってしまいます。とっても楽しいですよ。
エコリンピック?
2015.9.10
9月12日(土)は運動会です。台風が二つも来ていて、天候が心配ですが、必ず天気になると信じています。
今年の運動会のテーマは”エコリンピック~地球の大切さ”です。今年の年間の保育目標に「いのちの大切さ」があり、それを具体的に展開して行く中で、命を大切にするために今、自分たちができることは地球の自然やあらゆる命を大切にすること。それを競技の中に取り入れました。
種を集める種(玉)入れ、雑草を抜く綱引き、おいしい野菜を育てる畑のポルカ。自然をきれいにするためにごみをちゃんと分別する競技。大きな空にかける虹。天の川が見ることができるきれいな星空。昨年からブレイクしている三代目JSoul Brothersの”R・Y・U・S・E・I”に合わせてパラシュート。みんなの力と心を合わせて運動会を成功させます。運動会に取り組みながら、改めて環境の大切さ。幼い頃から自分たちで環境を守っていくことの必要を子どもたちも保育者も共に学びました。
また、エコを競技にすると、見ていてもとても楽しく、わかりやすく面白いです。子どもたちが一人ひとり命、自分、友達、環境を大切にしていくことを心掛けながら成長していってほしいと願っています。
親子遠足
2015.8.28
夏休みの間ご無沙汰しておりました。
今日、ファーム花茶にジャガイモとニンジン、枝豆の収穫に親子バス遠足で行って来ました。春からゆり組(年長)が種を蒔き、草抜きをしてきました。(でも、ほとんどは花茶さんがおいしく育ててくれました。)
おいしく実った野菜たちをたくさん収穫してきました。枝豆はその場でゆでてもらって食べてきました。毎年おいしいと思いながら食べますが、今年は一番おいしいと思えるのはなぜでしょう?
おいしいお弁当を食べて、ほっと一息。子どもたちは芝生の上で裸足になって遊び始めました。何か遊具があるわけではなく、何もないところで。何もない場所で友達との関わりだけで遊ぶ力は毎日の様々な経験の中で育まれます。でも、良かれと思い、早期教育、英才教育として知識を学ばせるため、子どもたちの遊ぶ時間と空間を充分与えなければ、この力は育ちません。自然の中で十分に体と心を動かし、友達との関わりを通して育った遊ぶ力。これはいずれ、生きる力、意欲となっていくものでもあります。幼児期の大切なこの時期。子どもたちの遊ぶ力に目を向けていきませんか?
杖
2015.7.16
杖を使いだして半年。(この年で杖を使うのはちょっと情けない)
まず、電車では必ず、席を譲られます。なんと優しい方々が多いこと。東京は特に、いくつも席が離れているのに譲っていただきました。遠慮しつつも、譲ってくださった方のご厚意をありがたくいただきます。
お店やエレベーターのドアも、遅い私を待っていてくれて。
申し訳ないと思いつつ・・・本当に感謝な思いです。
今までできるだけお世話をする立場でいようと頑張ってきましたが、それぞれに弱さや欠けがあり、年齢を重ねると、あちこち不具合が嫌でも生じてきて。労られる側になって初めて気づく、人の思いや、見えてくる世界。弱さや欠けを我慢しつつ持ちこたえながら、見せていただける、理解できる事柄もあって。弱さを持たなければ知らないでいたことに、自分の愚かさを感じ、恥ずかしく思います。自分が高慢で弱さに対してとても冷たい人間である事に気づかされて、悔い改めています。痛みを負ったことも世界が一つ広くなり、人の暖かさに気づかされた貴重な体験でした。これから治療して痛みがなくなっても、痛みを忘れずに、いたいと願っています。
ひまわり
2015.7.8
畑に種を蒔き、毎日水や肥料をやって大切に育てたひまわり。
でも、野生に生えていたひまわりの方がたくましく大きく育って
いることに気づき、愕然としたある教育者の言葉。
野生のひまわりはだれも水や肥料をくれないので、水分を
求めて自分で根を伸ばし、やがてしっかりした根になります。
畑で毎日水をもらったひまわりは何の努力をしなくてもその場
でも水をもらえるので、根を伸ばす必要がありません。
人の成長もある程度の環境を整えることは必要ですが、
多くを与え、準備しすぎると、自分から求め、伸びていく力が
育ちにくくなります。足りなさや欠けをどう自分で補うか?
どこを調べて情報を選択するか?失敗しながら、やり直し、
考え方を変えてみたり。試行錯誤しながら、時間をかけて
いく過程の中で太い、丈夫な根が子どもたちの心に育つのだと
思います。”早く芽を出せ!柿の種”よりも”ゆっくり芽を出せ
柿の種”土の中でゆっくりと育つことが大切です。幼児期は
その土の中で育つ時期でもあります。
いじめ?
2015.6.19
タレントのさかなクンのブログ?”いじめられている君へ”を読んでみました。メジナは海を泳いでいる時はみんな仲良く楽しく泳いでいるのに水槽に入れるとなぜか1匹を仲間外れにし、いじめが始まりました。かわいそうに思い、その1匹を別の水槽に入れました。残ったメジナは別の1匹をいじめ始めました。
広い海の中で泳いでいる時には何も問題がなかったのに、狭い水槽に入れると、いじめが始まる。
私の小学校3年の時の担任の先生が「人間はいつも自分が、誰かより優位に立って居ないと不安になる思いがある。だから魔女狩りとか奴隷制度など、ちょっと自分達と髪や肌の色が違うだけで、その人たちを差別して自分よりも劣るものとすることによって安心しようとするところがある」とおっしゃっていたことを
今でも覚えています。
私たちの心の中に誰かを自分よりも下の者として見下して安心する。それも大勢で一人を見下し、いじめるのが一番の安心なのかも知れません。でもそれはとても醜いやってはいけない心の動きです。
神様は私たち一人ひとりをそれぞれに違いをもって造られました。その互いの違いは神様に、それぞれに喜ばれるはずの物。それをいじめの原因にしていいはずがありません。互いに互いの違いを認め合い、感謝しつつ・・・
いじめのない社会になりますように!
ブランコ
2015.6.9
少し前まではどの公園にもブランコがありました。事故がいくつかあって、撤去されたり、設置されなくなった公園もありますね。ブランコはこぐためにタイミング、勢いが必要です。体の筋肉や体幹ができていないとうまくこげません。
また、幼児期は体を動かすと同時に心も伴います。楽しい!
面白い!恐い!もう一度やりたい!まだ無理!等様々な感情と
一緒に心と体で覚えていきます。そうやって覚えたものは自分の
限界がわかりますから、危険から身を守ること。そして更に前に一歩踏み出すことを自分で理解していきます。
確かに危険は伴いますが、遊具は幼児の成長に必要な機能を
もっています。皆さんも小さい頃、怪我をしながら、何回も繰り返しながら、覚えた遊びや身に着けたものはあると思います。思い出すとその時のドキドキした感情や、成功感も一緒に思い出せるのではないでしょうか?その感情が、大人になってからの勇気になったり、我慢になったりもします。安全の中であればちょっとの冒険が未来の力になります。お子さんと一緒に公園の遊具で体を使って遊んでみてください。
表現
2015.5.29
指導要録が6領域から5領域に変わってもうだいぶ経ちます。
保育をするにあたり、大切な目安であり、指針ともなります。
その中に表現という領域があります。自分を表現することは
とても大切です。自分はどんな性格なのか?今何を考え、何を
感じているのか?そして、この10数年表現することを教育の中で
必要以上に強いられてきてはいないでしょうか?どうしても
明るく元気にはきはきと挨拶ができる子、自分の名前、意見を
言える子が良いとされているような気がします。
でも、心の中に大切に持っている感情や、今はどう表現して
いいかわからない思い等。そっとしておいてほしい物も人には
あります。まだまだ未発達な子どもたちにとっても、どうやって
表現していいかわからない感情を共に寄り添って待ってもらうこと。表現の仕方を一緒に時間をかけて探してもらうことも情緒
を育てる、その子が育つためにとても大切なことではないかと
思います。どうか急がず、共に寄り添うことで、表現できない
思いを受け止めてあげてください。
初めてのお茶
2015.5.22
年長組は月に1度お茶(裏千家)のお点前を習います。3月には保護者の方をお招きしてお茶とお菓子でおもてなしをします。
今回は初めてでしたが、とても良い緊張感の中、先生のお話をしっかり聞いて取り組んでいました。
準備の時に、私が抹茶をこしているとYちゃんが「何をしているの?」と見にきました。「お茶の準備だよ」というと緑の粉を見て「お茶の用意?」こしたお茶を顔に近づけてあげると、「あっ!葉っぱの匂い」「そうそうお茶は葉っぱからできているからね」そう答えながら、大人はこの粉を抹茶と知っているからこの
かおりは抹茶のかおりと決めつけてしまっていますが、子どもはそれを素直に原体験から「葉っぱの匂い」と感じました。子どもたちの素直な感性に目が覚まされたような気がしました。
参観日
2015.5.18
参観日
子どもたちの様子を見ることと、お母さま方の親睦を目的に全員でゲームをしました。”1月生まれのお友達み~んな出てきて踊ろうよ♪”とそれぞれ、お母さま方も生まれ月に出てきて踊りました。年を重ねると誕生日はあまり重要ではなくなりますが、お子さんの誕生日は大切にしますよね。でも、誰にとっても誕生日はとても大切な大切な日です。プレゼントがあるかないかではなくその人がこの世に命をいただいた大切な日。何歳になっても。