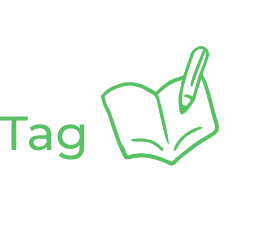新年あけましておめでとうございます
2016.1.2
比較的、穏やかなお正月をお過ごしではないでしょうか?
私は今、パワーポイントの作成に奮闘しています。PCを操作することも苦手なのに、プレゼンの作成のための資料集めは結構大変です。グラフや写真も入れながらの作成になりますので、テーマを決めるところから悩んでいました。その資料集めをするためにインターネットを検索していた中に、「ビルゲイツなど世界の有名な成功者は月に何十冊と本を読んでいる」という記事がありました。年収が減るほど読書率が低いという調査報告が上がっていると。活字離れが心配されてもう何年も経ちますが、私自身も前に比べてこの2,3年読書率が低下しています。年収を上げるとか、有名になるというのではなく、本を読むことで、広がる視野、積まれる知識、知らなかった感情や体験。人として豊かに成長するためには本を読みながら、自分の中で様々なことを感じ、想像することはいくつになっても必要なことだと教えられました。それで、今年、新しい年は私自身一つのテーマとして本を読むこと!様々なジャンルに挑戦しようと思っています。今年の終わりに何冊読んでいるか、楽しみです。絶対に三日坊主で終わらせないように頑張ります。
皆様にとってこの年が祝福豊かな年となりますように!
後伸び脳
2015.12.24
国際大の教授がよくおっしゃっている言葉です。よく言われている北海道の学力水準が全国で47位の最下位。でも高校生になると31位に上がります。学力テストの評価の範囲は人間の持っている可能性のどのくらいの部分を示すのでしょう?どんなに偏差値が高くてもどんなに学力の高い大学を出たとしても、社会に出てから、どれだけ周りの方々と良い人間関係の中で、仕事を進められるか?出世や、収入に関係なく、やりがいのある仕事、周りから必要とされる自分。必要とされなくても自分が満足する人生を歩めること、それを築いていける力を持つことが大切ではないでしょうか?北海道の子たちが幼少期に十分に体を動かし様々な経験を積みながら大きくなること。すぐに学力に反映されなくても、それは確実にそれぞれの生きていく土台を固めているのであれば、47位を嘆くことはないと思います。あせって試験の点数だけを上げようと詰め込みの学習、必要以上の競争意識を持たせるのは、いかがなものでしょうか?
幼少期、児童期は目に見えない土台固めを大切にしたいと思います。
クリスマス
2015.12.11
日本も世界もみんなお祭りが好きですね。クリスマスも世界中でお祝いされています。やはりサンタクロースにプレゼントをお願いするのが子どもたちにとっては楽しみですよね。子どもたちに何をお願いしたのか聞くと、ヒーロー物のアイテムやキャラクター物などと、やはりゲーム機器関係のものが多くありました。
ファミコンや、IT関係のゲームソフトなどで遊ぶと心配なこととして「想像力が養われない」というのがありました。サンタクロースに会った事はないけれど信じている想像力のたまもののような存在です。そんなサンタクロースに想像力を育てないものを願っていいのかなあ?と、考えてしまいました。クリスマスには想像力を豊かにするものを贈りたいですね。
子どもたちだけでなく、保護者の方々にも素敵な祝福豊かな
クリスマスになりますように!
歌う?
2015.12.4
12月に入りました。今、幼稚園ではクリスマス会の準備です。クリスマスはイエス様の誕生日。聖書に書かれていることを忠実に生誕劇をします。その中には讃美の曲で子どもたちが歌うのが5曲。とっても楽しそうに歌う子。小さな口で恥ずかしそうに歌う子。大きな声の子。小さな声の子。それぞれの個性があふれています。
「ようくピアノを聞いてね。」「お友達の声も聞こうね」
早くなったり、ずれてしまう子たちに促します。幼いながらにピアノに合わせること、お友達の声を聴こうとします。皆の声が合わさるととっても気持ちよく、嬉しく讃美できます。
周りの友達と気持ちよく生活していくこと。大切にしたいですね。
愛しているから叱るんです!
2015.11.20
まだ、クラス担任をしていた頃、後輩に対して仕事を教えている時、出来ていないところや、間違っている所を指摘したり、正してあげる時、決して良い気持ちではありません。言わないで済むなら言わないでいたい。誰かほかの人が言ってくれないかなあと思っても、その先生のため、子どもたちのため、言わなければ!と。言われた相手も傷つき、落ち込んでいるだろうなあと自分も傷つきながら、伝えた覚えがあります。でもそれは今も変わらず、言いにくいことを心を鬼にして言いつつ、相手の成長を待ちます。お母さん方もそうではないでしょうか?
怒りたくて怒っているわけではなく、躾であったり、善悪の基準だったり。叱ることで子どもが成長するために。痛みを覚えながら叱っていく時、互いに成長していくのだと思います。愛していない子、どうでもいい子はほっときます。大切だから、愛しているから叱らずにはいられないのです。
叱っても回復力はあります。だから叱れるんです。
成長痛?
2015.11.6
今朝、6歳の子が「先生、ここが痛い」と膝をさしてきました。ぶつけたわけでも、傷がついているわけでもないので、「きっと成長痛だよ。」と言うと不思議な顔したので、「○○ちゃんの体が今急いで大きくなるための痛みだよ。病気じゃないから大丈夫!」と言うと納得して遊びに入っていきました。その時にふと、私たちの心の痛みの事が浮かんできました。
若い時に人間関係の中でどうしてもうまくいかない人がいてその人をどうしても許せなくて、苦しんでいたり。自分の失敗や出来ない自分を責めて責めて悩んだり。そんな時に聞いたのが、「心の受け皿を大きくする為にはその器を一度壊して大きくするから、痛むのは当たり前。心が大きくなるためです。」
年を重ねた今では多少の物事にはだいぶ感情を左右されず、受け止めることができるようになってきてはいます。でも、まだまだ落ち込んだり、悩み続けたり、若い時よりも深い課題が与えられたり。体の成長はそれぞれ、ある程度の所で終わりますが、心の成長はまだまだ続くようです。でもそれはまだまだそれぞれが成長し、変わりうる可能性があるということ。
悩みのない方はいらっしゃらないと思います。今抱えていることは、必ず自分を大きくしてくれます。辛い時には無理をせず、持ちこたえているだけで十分です。そうしているうちに成すべきことが見えてきたり、一歩前に出る力が出てきたり、誰かが助け舟を出してくれたり。
心の成長痛。まだまだ成長する期待度が高いということです。でも、あまり一人で悩みこんでいる時は私で良ければお話聞きますから、遠慮なく声を掛けてください。子育て相談ではない課題でも良いですよ。
○○も誉めれば木に登る
2015.10.30
私は少しだけ縫物ができます。男の子のお遊戯で法被が2枚そろわなくて、6枚の前掛けになっていた布を2枚の法被に仕上げました。男の子たちに持っていった時に「すごい!」「尊敬する!」と誉められて、元気がでました。
私は少しだけ絵に自信があります。「ブレーメンの音楽隊」の小道具で、泥棒のごちそうを描いて子どもたちに見せたら、「天才なんじゃない?」「画家になれば!」と言われ、木のてっぺんまで登りました。
子どもはよく誉めて育てると言いますが、誉められて良いお母さん、良いお父さん、良い先生になるのは私たち大人も同じです。子ども達以上かもしれません。
わけても、主婦のみなさんはお家の中で誰かに認めてもらうことはあまりないと思います。当たり前のように掃除、洗濯、食事の支度が出来ていることにもっともっとねぎらわなければならないと思います。主婦の方々、日常の様々な事をこなしながら育児をすることは本当に大変です。当たり前のことではありません。尊敬に値します。手を抜いていたとしても、ちゃんと家族がおなかをすかせず、心地よいお布団に寝れることは、主婦の方々の日々の努力があるからです。無理せず、自分の時間も大切にしながら、今日のなすべき分だけ、頑張りましょう!頑張りすぎはよくありませんよ。一息入れて!
気づき
2015.10.23
「先生、あれ使わなくなったね」と言われ、あれ?杖のことです。
7月に杖の事を書かせていただきました。7月の末に両股関節の手術をして、今は筋トレ、リハビリ中ですが、とても順調です。
「先生、杖なしで歩けて良かったね」と言ってくれる子も。なんて優しい子たちなんでしょう!優しい心。優しい言葉がけ。表現する事があまり得意ではない日本人ですが、このまま大きくなってほしいと願います。また、自分のことだけではなく、周りの人の変化や様子に気づいていく目と耳と心?気づきがなければどんなに優しい心、言葉を持っていても、何にもなりません。見て見ぬふりではなく、様々なところに気づきつつ、自分の精一杯を表現できる子になっていければと祈りつつ・・・
おはなし
2015.10.8
”むかし、むかしあるところに”と寝物語に祖父母や両親に話してもらった経験、皆さんもあると思います。私の小さい頃はまだまだ絵本もすぐに手に入らない、文化的にも貧しい時代でした。ですから、父や母から聞く昔話はとてもとても楽しみでした。私の両親は教育者などではありませんから、レパートリーも少なく、「ももたろう」「こぶとりじいさん」「はなさかじいさん」程度で、もう種が尽きてしまいましたが、それでも親から聞くお話は何度きいても楽しみでした。聞いた話を自分の頭の中で想像しイメージを膨らませます。
でも、今はテレビや漫画、アニメーション映画等、自分が想像する前にすでに画像と音があるため、各自がイメージを膨らませる余地が少なくなっているようです。
そして、お話は”言葉”だけでイメージを膨らませるのではなく、感情や状況までも考え、感じることができるのです。すばなしは幼児期の心に、脳に豊かな刺激を与えます。イメージを膨らませるために、集中力、思考力、言語力等様々な力を使います。
おはなしは親しい人の肉声で聞くとても貴重なすばらしい経験です。この幼児期にたくさん経験させてあげてください。
やればできる!
2015.10.2
ある日の朝のラジオで流れていたものです。
高校生の時に担任に「やればできるなら、最初からやれ!」
今、確かに「やればできる子だよね」のようなことがよく言われていますね。
でも、やればできるのは分かっていてもなかなか腰が上がらず、本当にできる物かも見えていない時には前向きになれないことも多々あります。何度かそんな経験を通って初めて、やってみることに一歩踏み出せるのかもしれません。であれば、幼児期の
今は海のものとも山のものともわからない。ただ、可能性は充分に秘めている子ども達。「やればできる」でも、焦らず、励まし、やる気が出るまで待つこととやる気が出る経験をさせることと、一緒に様々な事を経験していく時間をゆっくり過ごすことが大事ではないでしょうか?