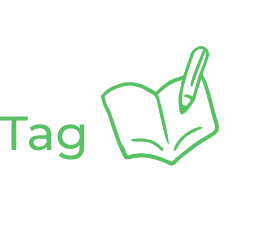ひとこと
2017.5.1
三浦綾子さんの本の言葉でできているカレンダーがあります。
「自分一人ぐらいと思ってはいけない。
その一人ぐらいと思っている自分に、たくさんの人がかかわっている。」
三浦綾子著 『人間の原点』
説明に「ある人がでたらめに生きるとその人間の一生に出会う
すべての人が不快になったり、迷惑をこうむったりするのだ。そして不幸にもなるのだ。」とありました。なるほど、私たちはやはり一人では生きていません。必ず何かしらの影響を与えてしまいますし、受けます。
私は説明を読む前にこの言葉を違う意味にとらえていました。
「自分一人ぐらいいなくなっても何も変わらない。誰も悲しまない。なんて思わないで。その一人には必ずたくさんの人がかかわり、その存在を大切に、必要に思っている人がいるよ。」と。
言葉というのは不思議です。奥が深いです。同じ言葉でも様々な取り方が出来ます。同じ人でも時が変われば、違う意味で響いたりします。言葉はひとを励まし、勇気づけもしますが、傷つけ、落ち込ませもします。褒められて成長する子もいれば、叱られて大きくなる子もいます。どのような言葉を発するにも大切に使いたいと思います。
みんな一緒
2017.4.28
日本人はみんな一緒と言われると安心して沈没しそうな船から海に飛び込めるという笑い話を聞いたことがあります。今の小学生や中学生もクラスの中で良い意味でも、悪い意味でも目立たないようにするという傾向があると聞きます。
少し前、水色が流行ると小学生がアウターからランドセルからみんな水色でした。2~3年前は卒園式の女の子たちの衣装はほとんどAKB48風でした。色々な意識や価値評価があり、国民性でもあるとは思います。でも、私たちは一人ひとりみんな個性豊かにデザインされています。顔が似ていても、性格が似ていても同じ人間はいません。その個性を発揮し、互いの違いを受け入れ合い、、成長していく事で相手の気持ちを理解でき、わかりあえていきます。みんな一緒の考え方の方が何をするにも楽です。でも、違いを受け入れあう事は相手を理解しようとするための努力や時には我慢だったり、引いたりしなければできない事で互いに苦労します。でもそうして人間関係を築いていく事でより豊かな信頼関係が育まれるのではないでしょうか?
何かが流行った時にみんな同じでなければ安心できないのではなく、それぞれの違いを幼い時から受け入れられるように成長していってほしいと思います。
行きて帰りし物語Vol.Vol.2
2017.4.18
新学期が始まりました。入園して来たお友達も少しずつ慣れて落ち着いて来ました。進級した子たちもお部屋が変わり、担任が変わり、新しいお友達も加わり新しい環境になじんできました。年少児、年中児が一つ上のクラスになることは本人たちにとっては大人が考えているよりもプレッシャーのようです。大きな期待と嬉しさの反面、今までの年長組さんへの憧れがあればあるほど、そうなりたいという思いから、緊張した様子で登園してきます。
そんな緊張がほどけてくると、ふっと元のお部屋に間違って行ってしまう子が少なくないです。気が付いて慌てて新しいお部屋へと恥ずかしそうに走っていきます。その中で、意識的に?無意識に?元のお部屋へふらっと行く子がいます。嬉しい事もあり、誇らしげに一生懸命進級したクラスで頑張っていますが、ふっと一息つきたいときがあるようです。
前回”行きし帰りし物語”でもかきましたが、実際の生活の中で元の場所へ戻ってみる。お母さんに甘えるだけではなく、元の自分を確かめてそして一歩また踏み出して行く。日常の当たり前の流れの中でも子どもたちは大きな冒険を経験しながら一日を過ごしています。そしてそれは私たち大人にも言える事ではないでしょうか?
自分をつくっているもの
2017.3.18
先日無事に卒園式を終えることが出来ました。満3歳、3歳、4歳から入園してきた子たちが4月には小学校です。入園したての頃を思い出すと今の姿は心も体も大きく成長しました。
卒園式に出席するにあたり、朝早く起きて着物の支度をしました。裾の長さを合わせ、襟元を整え、何度やってもうまくいかない帯を慎重にしめながら気づいたのは「着物を着る文化や着ることができるようになった部分は着付けの先生につくられている」という事でした。そうなると、読書が好きな部分は小学校6年の時の先生の影響。縫物や料理が好きなのは母の影響。自分自身が今在るのはたくさんの方々の支えや教えによってである事。
卒園していく子どもたちも様々な先生や友達に色々な影響を受け、ご家族の温かい愛の中でその子自身がつくられたのだと思うと、周りの方々みんなに感謝な思いでいっぱいになりました。そして更にこれからも多くの方々との出会いの中でそれぞれが自分らしく存在していく事。生まれてきた良かった。喜べる人生を歩んでほしいと切に願います。
マリつき
2017.3.10
昨年の11月くらいから、ボールをつく事に取り組んでいる子がいました。なかなかうまくつく事が出来ずにいました。3回ついたら、足にぶつかって転がったり、何度やっても、何日やってもうまくできずにいました。それぞれに得て不得手があってすぐにうまくできる事、何度もやってみないと出来ない事がありますね。できない事に取り組むのは大人にも困難な事です。
でもついこないだ、その子がとても上手につけるようになっていました。毎日少しずつ諦めずに頑張っていた成果です。遊びの中で子どもたち一人ひとりがそれぞれのやりたい事、乗り越えたい事、克服したい課題に取り組むために、自由な時間と場所が必要です。その保証をしていくのが教育現場でもあると思います。それぞれが自分から主体性をもって取り組む課題。それを達成しようと、日々、様々なかかわりのなかで、自分なりに時間や場所をみつけて取り組めること。そして達成したことはその子の力となり、自信となります。マリつきという些細なことですがその
その積み重ねが土台となり、その子自身が形成されてい来ます。保育の専門性をもって保育者側から提供するもの、そして子どもたちがそれぞれに取り組む時間と空間をしっかりと保障していきたいと考えています。
成 長?
2017.2.16
”行事が一つ終わるごとに子どもたちはそれぞれに成長する。”それはこの仕事について初めての運動会を終えた時に気づき、大きく感動した事でした。その事実は今も裏切られてはいません。
どこが成長しているか?と言えば、子どもたち一人ひとりそれぞれですが、何かが出来るようになったり、今まで以上に多く、高く飛んだり、回ったり。目に見えてわかることもしかりですか、一人ひとりが自信をつけているというのが一番だと思います。どうしても運動神経の良い子やダンスのセンスのある子などが目立ちます。目立たないで、終わる子もいますが、その子たちこそ、心の成長は大きいと思います。何度もやり続ける粘り強さや、失敗した時の悔しさ。そして成功した時の達成感等。
また、大切なのは行事のための準備というより日頃の保育がどう行われているか?です。日々の中でそれぞれが十分に自己表現ができ、周りに認められていることが根底に必要です。
幼児期は特に見えない所の成長が大切です。そこに目を止めていけるよう心がけたいですね。
どうしたの?
2017.2.3
朝のホールでAちゃんが泣いていました。聞いてみるとBちゃんに意地悪なことを言われたらしく、そのBちゃんもそばに居ます。「意地悪なことを言ったの?」と聞くと「うん。でもごめんねしたよ。」「許してあげられる?」「うん」と言ってまた仲良く遊びだしました。お友達を泣かせてしまった時に、すぐに謝る事、子どもにとっては難しい事であり、許すことも難しいと思います。感情が伴わないとすぐに、許すことはで来ません。相手に泣かれた時も、自分の悪かったところを理解するためには時間
がかかります。幼い今、様々な感情、葛藤、理不尽さに出会いながら、心の中にしっかりと土台を築いてほしいと思います。でも、謝罪、自分の非を認める事、相手を赦すことは大人の方が難しいかもしれませんね。
そして次は壁に顔を伏せているC君。「どうしたの?」と心配して声をかけると、迷惑そうに、「かくれんぼの鬼しているの‼」すみません。余計な声かけでした。確かに、泣いているように見えましたが、かくれんぼの鬼でした。すみません。
3学期始まりました
2017.1.30
昨日から3学期が始まりました。今日も全員出席で元気いっぱいの子どもたち!早速今朝は隣のすずらん公園で雪遊びを楽しみました。ウェアーの着脱、靴に雪が入らないようにつけるカバー等、園の集団生活の中では出来るところまでは自分で頑張ってもらいます。最初にしっかり伝える事で何度か助けるだけでちゃんとできルようになります。
今日3学期初めての外遊びでしたが、とてもスムーズに自分たちの支度が出来ていました。ご家庭でも頑張っていることがうかがえました。ありがとうございました。
靴カバーを外して、脱いで、ついてる雪を落として、乾かすためにホールまで持って行くという一連の動作は大人には聞いてすぐに行動に移せても、いつもと違う動きであり、体の小さな子どもたちにはその動作から大変なところもあります。それを一人ひとり、丁寧にお教えていくには忍耐を要します。私もまだまだ未熟ですから、言葉の使い方が乱暴になったり、「早く!」を連発したり…理想の優しい先生像にはほど遠い現実があります。
ドッチボールのようなルールがある遊びを教える時も最初は先生の言葉ばかりが行き交い、ゲームにならない状況ですが、何度か回を重ねるうちに形になって行きます。いつも最初は大変ですね。でも最初を丁寧に伝え、一人ひとりが理解するともう大丈夫。この最初の関わりをしっかりすることで信頼も深まります。ちょっと言葉も荒くなっても、それが子どものためです。
明けましておめでとうございます。
2017.1.1
新しい年が来ました。2017年にどのような期待をし、希望を持っていますか?この年が祝福豊かな年になるように祈っています。
友達から1ヶ月毎の卓上カレンダーをいただきました。月毎に素敵な写真が付いていますが、その中に必ず私の名前が入っています。空を飛ぶ気球の模様の中、素敵なお家の表札等。最初はちょっと恥ずかしくも思いましたが、見ていくうちに、自分の名前を今まであまり大切にしていなかったことに気づかされました。仕事の上では園長としての顔でいることがほとんどで、忙しくなると家に帰っても仕事の事から解放されないでいることも多く、自分というより、園長でいることが多くありました。このカレンダーを見て、“MICHIYO”という名前を確認し、自分でいることの大切さを思わせられました。ですから忙しい時には特に肩書きのない自分自身でいることを心がけようと思います。自分を大切にしていなければ、本当の意味で相手を、子どもたちを大切にできません。自分のために、周りのために自分を大切にすることはとても大切なことだと思います。
行きて帰りし物語
2016.12.20
私は56歳になった今でもファンタジーが好きです。中でも王道ですが、トールキンが好きです。冒険に出て行き、また元の所に戻って来る。元の場所はいつもと変わらない日常で、当たり前で、普通の毎日。でも、帰って来た自分は見た目は変わっていなくても、内面は変わっています。成長しています。
子どもたちが幼稚園に来るのも同じです。毎日毎日お母さんのひざ元から幼稚園に来てお友達と仲良く遊んだり。時には喧嘩をしたり。楽しい事があれば、嫌な思いをすることもあります。そんな様々な事を経験して帰り行く場所は家族の元。そこで、安心して守られてまた、明日元気に登園。子どもたちにとっては毎日の幼稚園は冒険そのもの。命の危険はありませんが、様々な挑戦があり、喧嘩があり、できなくて落ち込む事。そして頑張ってみんなに褒められること。その繰り返しの中で、人として生きていくための土台を作っていきます。
幼い子を集団の中に入れることはとても勇気がいることで、保護者の方々もそれぞれの葛藤があるのはわかります。待つ方も心が鍛えられますね。保護者の方がゆったりと自分を待っていてくれるところがあるから安心して冒険に出られます。出て行く方も待つ方も、それぞれに豊かに成長し続ける日々です。
何も変わっていないような毎日ですが、みえないところでは日々、変化しています。子どもたちを子どもたち以上に信じてあげてください。子どもたちは私たち大人を過大評価しています。必ず、守っていくてくれる。最後まで味方でいてくれる。その期待に応えるのは特別な事ではありません。「ちゃんと見ているよ。ここにいるよ。」といつもの所で見ていてくれればいい
のです。
子ども以上に信じるという事は失敗しても大丈夫。できなくても変わらずに愛しているという事です。過度な期待をかける事ではありません。