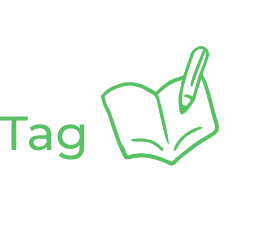ご無沙汰しました
2018.5.25
言い訳です。忙しさの中で、3か月以上も更新していませんでした。
書きたいことはいくつかありましたが、それも埋もれてしまい・・・
反省です。
先日、初めてのお茶の日を年長組で行いました。月に1度、日本の伝統的な文化である茶道に触れる目的で行っています。年に11回茶道の先生にご指導をいただいています。
子どもたちも、この時間が大好きです。茶道の先生の纏う空気で子どもたちの向かう姿勢も一変します。とても良い緊張感の中で進められます。背筋が自然に伸びます。
「これが抹茶です。」とおっしゃった先生の言葉に子どもたちが集中します。今までに見たこと、聞いたことがなかったこと、知らなかったことを心と体と脳、全身で吸収ていく子どもたちのエネルギーに圧倒されました。新しいことを知ること、吸収することはいくつになっても大切な事であり、また、幼い時に本物に触れることがとても貴重な体験になることを改めて感じました。
マイナス23℃
2018.2.2
今週は朝の気温がマイナス20℃超え。北海道冬本番ですね。
それでも子どもたちは雪遊びが大好きです。顔に雪がかかって
も、多少足が冷たくても。
でも大人はそこに寒くはないか?かぜをひかないか?靴下を
もう一枚増やすか?と遊びを中断したり、子どもに雪、冬のマイ
ナス的な感じを与えてしまったりします。
大人は何度か繰り返す、季節の中。そして遊んでばかりはい
られず、除雪や寒さ対策の大変さを熟知しているので、どうして
も冬に対して消極的です。子ども達にはまっさらな感覚で、冬を
十分に楽しんでほしいと思います。また、私たち大人も冬の良
い所を見つけながら、マイナス23℃というめったにない体験を
貴重に感じていきましょう。
言葉と態度で
2017.12.26
満3歳のA君が年長のお姉さんたちにかわいがられているのを見て年長のB君が「おれもかわいがられたいな」と一言。確かにB君はいたずらや、ちょっとわがままを通して叱られるのが多いかもしれない。
でも、感じ方もちょっとネガティブの傾向が・・・「B君のこと、どうでもいいと思ったらだれも叱らないよ。B君の事大好きだからちゃんと叱ってくれるし、先生たちもお父さんもお母さんも大好きなんだよ」と言うと納得してくれました。
同じようにかわいがっても十分届く子。どんなにかわいがっても足りないと思う子。それぞれです。きっと日本人には苦手ですが、折りにふれて「大好きだよ」「大切だよ」ということを言葉と態度で示していかなければならないところでもあるんですよね。
また、その子も我慢をするのではなく、言葉にして伝えてくれたことはとてもよかったと感じました。十分かわいがっているつもりが届いていないのだとしたら、それも悲しいことです。お互いが十分にその気持ちを伝えられることはとても幸せですね。
この一年様々な方々に愛されお世話になりましたことを感謝します。
また、気づかないところで多くの方がたに迷惑をかけ、傷つけたのだろうと思い、申し訳なく思っています。ごめんなさい。
皆様にとってよき年がきますようにお祈りしています。感謝をこめて。
また来年。
冬休み
2017.12.22
「私、冬休み大っ嫌い!」「明日から冬休み嫌だ!」
子どもたちの素直な言葉です。園が楽しくって良かった。休み中
ご家族との貴重な時間を過ごしてください。今、この年齢でしか
体験できない事。この時期にしっかりと家族に甘えること。大事
です。
2学期も大きなけがや事故もなく無事に過ごせたことが何よりの感謝です。普段の当たり前は普通の事ではなく、無事に過ごせることは何にも代えがたい幸せであること。いつものように朝がきていつものように夜になる。今のこの平和が守られるように!そしてそのことに気づいて感謝できるように!
4月には言葉が出ていなかった満3歳の子も一生懸命楽しかったことを私に自分のもっている言葉を駆使して伝えてくれます。自分から気づいてお手伝いをしてくれたり。お誕生会の手作りおやつの御礼をわざわざ職員室まで言いに来てくれたり。それぞれが周りの友達や家族とのかかわりの中でそのコミュニケーションを豊かにしています。人として生まれてきた喜びの一つは共感できる事。友達と共に笑って、喜んで、悔しがって…子どもたちが一人ひとり確かに成長していることが伝わり、感謝です。
この年の皆様のご協力とご配慮に心より感謝します。ありがとうございました。良いクリスマス、良いお年をお迎えください。
絵本読んであげる
2017.12.5
年長さんが小さいお友達に絵本を読んであげています。朝陽がさすホールの片隅の暖かな空間。その様子を見ているだけで幸せな気持ちになりました。
絵本
2017.12.5
絵本は子どもたちが字を読めるようになったら自分で読ませるようにしますが、絵本は読み聞かせるもの。読んでもらうものです。
朝、泣きながら登園してきた子に、その子の好きな絵本を読みました。
1回目。2回目と読んでいくと自分の好きなところにくるとふっと泣きやみます。3回目になると、すっかり機嫌もなおり、遊び始めました。私たちもそうですが、落ち込んだり元気がない時に、物語や、好きな歌などの自分の好きな、元気をもらえる場面や言葉などに力をもらい、気持ちを立て直す時があります。
絵本は心に元気を与える力があります。また、読んでくれた人のぬくもりや声の暖かさ。その時の空気感まで思いだし、自分が愛されていること、大切にされていることを心と体で思いだします。
そしてその経験を今度は小さい友達に伝えていきます。たどたどしい読み方ですが、小さい子たちは黙って聞いています。そんな関係と時間と空間を守っていくことの大切さを日々思わせられます。
夢のなる木
2017.11.20
今日は星槎道都大学のお兄さんお姉さんが来てくれて夢のなる木を一緒に作りました。魚博士になりたい❗セイラームーンになる❗サッカー選手になりたい❗色々な夢を描きました。
朝のかおり
2017.11.16
Aちゃん「おはよう!今日も宇宙に行こう」
Bちゃん「うん!行く!行く!」
宇宙に行く遊びって何をするのか聞いてみると「鉄棒で逆さまになるやつ!
全部さかさまに見えて面白いよ!」
Cちゃん「今日、パン食べて来たんだよ」「おいしかった?」「うん!あ?サンドイッチもパンだよね?」「そうだよ」
お母さんの作ってくれたサンドイッチがおいしかったこと、ちゃんとお母さんが朝ごはんを用意してくれることの幸せを感じました。
D君「今日ね、帰ったら新しいリュック買ってもらうの!」とっても嬉しい報告
E君「縄跳び壊れちゃった」「大丈夫。直しておくね」とボンドを取りに教材室へ。
こうしていつもの朝が始まっていきます。それぞれの子どもたちとの様々な会話。
その一人ひとりの成長や今日の健康状態。情緒を感じとりながら・・・
今日も一日平和に守られますようにと祈らずにはいられません。幼子たちの世界が日々守られていることに心から感謝します。
新体操部?
2017.11.2
朝の登園時、おうちで作ってきた新体操の競技用のリボン、トイレットペーパーの芯にスズランテープをつけて楽しそうに踊っていました。私も!作る!とちらしを細くくるくる巻いてスティックを作りその先にリボンをつけて出来上がり。子ども達のところにもっていくと、次から次と注文が来て。「作ってみよう」と子どもたちの中へ渡しました。そのあと、もも組さんのお友達が新体操で盛り上がり、元気にステージで発表?していました。子供のかわいさ、元気さ、行動力をさらに豊かに育てていきたいと思います。
収穫感謝会
2017.10.27
今日は収穫感謝の会がありました。日ごろから様々なものが豊かに与えられていることに感謝しました。
ご家庭からジャガイモ、人参、玉ねぎなどカレーの材料と果物のご協力をいただきました。とてもたくさんの野菜も果物も集まり本当に感謝な時でした。また、ユニセフの方々にも来ていただき、世界の中では5秒に一人の幼い子が飢餓でなくなってい
ることや衛生状態が悪く、病になる子。そして日本の一週間分の食事と飢餓で苦しんでいる国の食料の差を見せていただき、日本の私たちはなんと豊かの中にいるのかと、思わされました。パワーポイントを見たあと、親子で感想を話し合いました。
「かわいそうだと思った」など、子どもたちも小さな心で感じたことを表現していました。
そして今ここにいる園児たちの中からこのような問題に取り組む子たちが起こされるようにと願います。私たちにもできることはまだまだあるはずです。もっともっと考え、具体化できることを実行していきたいと思います。