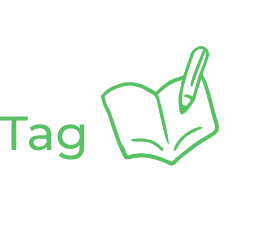朝の子どもたち
2019.6.12
「おはよう‼」と元気に登園する子。
なかなか挨拶ができない子。
小さな声で「おはよう」とようやく絞り出せる子。
それぞれにその表情は毎日違います。保護者のかたがたと離れて、「今日何して遊ぶ⁉」と意気込む子もいれば、保育者の膝の上でしばらくゆっくりと周りの様子を見る子。保護者が仕事に行ってしまったさみしさをどうおさめようか?時間がかかる子。保育者は登園してきた一人ひとりの様々な思い、様々な感情思に寄り添えるよう努力します。
とてもとても忙しくなってしまった、今の社会の中で懸命に働かれている保護者の皆さん。毎日お疲れ様です。もっと子どもたちと向き合いたい。もっとゆっくり一緒にご飯が食べたい。お風呂に入りたいという思いがありつつも、許されない現状があります。忙しい時間に預かってもらうだけでは子どもは安心して成長できないと思います。その時々の思いを受け止めてくれる誰かがそばに居なくてはと。保育者として子どもの隣に寄り添う者として十分とは言えませんがそれぞれに子どもたちの思いを受け止めつつ、平和に安心した1日を子どもたち一人一人が過ごせるように!願っています。
今目の前の子に!
2019.6.7
幼い命が失われる事件、悲しい親子殺人が毎日のように報道され、心痛める日々が続いています。虐待をする親たち、引きこもりの息子を心配して殺人をおこした父親。多くの方々を傷つけて自死してしまった方。殺人を犯した方にはやはり、”愛着障がい”が見え隠れしています。乳幼児期に愛情をもって育てられることの必要性です。今、ニュースで報道されていることは10年20年前に防ごうと思えばふさげたことでもあります。ということは、今、目の前にいるお子さんたちをとにかくかわいがって育ててください。乳幼児期だけではありません。小学校に行っても中学生でも話したいことをすぐに話せる親がいつもそばにいてくれることが大切です。お仕事をもっている保護者のかたがたには忙しさの中で難しい所ではありますが、できるだけ、今向き合うときは向き合い、話さなくてもそばにいてくれている。自分を見ていてくれるという信頼を築くことです。後悔をしないためではなく、親子、家族の関係はこの信頼関係があってこそです。今この時期はもうきません。今を大切にしましょう。
どっちにする?
2019.6.4
何かを選ぶときに選べない人がいます。今日着ていく服や、どのケーキを食べるか等を決めるのはそれほど後々に大きな影響はありません。でも、日々の中で、家族の健康に関わる事や、将来に影響する判断もあります。前にも書きましたが、毎日の中での何げない小さな決断が大きな決断をする訓練になります。そして子供は親がどんな判断をしているかを見ながら成長して行きます。でも、今は選択する力量や知恵がないうちに子どもたちに多くのことを選ばせているような気がします。朝、子どもの様子を見て園を休ませるかどうか?子供に聞いて判断する保護者がいると何かで読みました。保護者のかたがたにも今からでも遅くありません。判断には責任が伴いますから、そこを避けたい方々が多数であることはよくわかります。でも、お子さんたちが人生を豊かに生きていくためには様々な多くの判断が必要です。その判断ができるように育てていくには今この幼児期の小さな判断の積み重ねです。そしてそれはまだまだ間違ってもいいのです。間違ったらまた、やり直せばいいのです。保護者が判断するところや間違ってもやり直して前に進むところを見せていくことで、子どもたちも失敗を恐れずに進んでいける子に育っていきます。失敗をしてもまた、そこから違う方法で進んでいけます。どうか大いに間違ってください。そしてやり直すことは恥ずかしくないことをお子さんたちにちゃんと伝えてください。それが家庭の教育力です。応援しています。大事なのは間違えることなく成功することよりも間違えた時にやり直すことができることです。
一期一会?
2019.5.13
「一期一会」一生に一回限りのこと。生涯にただ一度会うこと。と辞典にあります。
いつも会っている家族や友達。日常の中では誰ともいつでも会えると思っています。幼稚園で朝出会ったお子さんがそのままの姿で帰せるように祈りつつ、願いつつ保育をしています。でも、不慮の事故はどんなに環境を整備し安全に整えても起こるときには起こります。これだけは絶対におこらないように願いつつ細心の注意をもって保育に当たります。
今回の大津市の事故で掛け替えのないお子さんをなくされたご家族にとっては信じがたい出来事でした。一生に一度しか会えない方に心を込めて、お茶を差し上げること。これは毎日会える家族や友達にもその思いをもって大切にもてなし、関わっていくことがとても大事ではないかと思わされました。毎回会える方にも、家族にも今できる限りのことをしてあげること。でもそれには限界もあります。そしてできれば失敗したとき、傷つけてしまった時には次回に謝ることができる機会が与えられることを切に切に願います。すべての尊い命が大切に守られますようにと願わずにはいられません。
尊い命
2019.5.10
大津市においての保育園児の事故で尊い命が失われました。失われた命に対する思いはどんな言葉でも表せないほどの悲しさ、苦しさ、悔しさ、怒り、理不尽な思い…でも当事者であるご家族や保育園関係の方々の思いはいかばかりかと察するに及びません。今はこのような事故が起こるとすぐに責任問題や賠償、再発の防止とどんどん先へ先へと進みます。今回は散歩の自粛の考え。今までにブランコの事故や滑り台の事故があれば、その遊具の撤去等。そうではなくて、今回は運転者の運転意識が問題であり、また、運転するもの全員がいまもう一度、ハンドルを握ることは命に係わる重大な責任を伴うことであることを認識することではないかと思います。私自身、自分の運転を見直し、殺人マシンに乗っていることを自覚して運転することをもっともっと心がけなければならないと再確認しました。けがをしたから、事故を起こしたから、その保育内容を見直したり、遊具を撤去するのではなく、どう遊んだら、安全に遊べるか?小さな失敗、小さなケガをしながら大きな失敗、大きなけがにならない訓練としてこの幼児期を様々な経験をさせることは大切だと考えます。ただ、今回のように取り返しのつかない事故に巻き込まれた時には、どう判断し、慰めの言葉も浮かびません。ただ、ただ、子どもたちの遊びの範囲が狭められないことを願っています。
空想のおはなし
2019.5.8
私 「おはよう」
A君「今日ね。夢見たんだよ」
私 「どんな夢見たの?」
A君「怪獣出てきたの」
私 「怪獣怖かった?」
A君「怪獣仲良しだった」
私 「何して遊んだの?」
A君「ブロックで消防車作ったの」
B君「僕もね、僕もね夢見たよ。」
私 「誰出てきたの?」
B君「アンパンマンとばいきんまん」
と満3歳の男の子二人と私の朝の会話です。この後もお話はどんどん膨らんでいきました。夢をどれだけリアルに覚えているのかはわかりませんが、聞かれたことに様々に考えて答えてくれました。もう一人の子もその会話に入りたくてちゃんと話の中に入ってきました。うその作り話としてしまうのではなく、昨今想像力の低下が心配されている中、満3歳の子にはこんなに想像力が豊かにあります。これを更に豊かに育てていくことが私たちの大切な責務です。お子さんたちと想像を膨らませられるお話しをたくさんしましょう。その中で現実との違いも分かっていきます。満3歳児の時にはちゃんと想像力が備わっています。これを日々の何気ない会話の中で育てていきましょう。
大型遊具
2019.4.26
今日から園庭に工事が入りました。大型の遊具を計画しました。砂場と泥で遊べる所。
クライミングができる所等。保育者たちと子どもたちが様々な遊びが展開でき、体を動かし、心を動かして遊べることを目指しました。業者さんともいろいろ話し合い、アイデアをもらって、昨年秋から着工しました。今朝、大きなと落暉からクレーンで運び出された10本の10mくらいの丸太。保育室から見ているとすごい迫力で子どもたちはくぎ付けでした。素材からできていく様子を見られることも予期せぬ収穫でした。こんなに近くでクレーンや丸太を見るのは私たちも初めてでした。完全な感性は来年になりますが、今期は5月末で完成です。どのような遊びが繰り広げられるかわくわくドキドキです。
遊びって本当に楽しく心躍りますね!
ご無沙汰しました
2019.4.19
先日、東京大学の入学式での祝辞がテレビで話題になってました。上野千鶴子名誉教授の祝辞でした。東大の新入生に向かい、
「あなたたちの頑張りをどうぞ自分が勝ち抜くためだけに使わないでください。」
「恵まれた環境と恵まれた能力を恵まれない人たちを助けるために使ってください。」
様々なところで話題にされていましたが、ふと気が付くと、内容は私たちが育てられてくる時に、誰かが、いつもどこかで言ってきたことではないかと思わされました。古き良き日本の教育はお互い様の中でいつも助け、助け合いながらお醤油の貸し借りから始まり、隣近所の様々なかかわりの中で育ってきたと思います。でも、昨今この言葉がこんなに新鮮に、感動的に聞こえるのは、言葉にして伝えなければ伝わらない社会になっているのだなと感じました。子どもたちを育てるうえで、そして人として生きていくうえでとても大切なことであり、誰しもが身につけて成長してほしいと切に願います。
と言う自分もまだまだ人のお役にたてているとは思えませんが、どんな形であっても誰かのためになっていく人生をそれぞれが創造していってほしいと考えています。
春になる
2019.2.21
学生時代に下宿生活をしている私の友達をよく招いて母はご飯をごちそうしていました。友達が「働くようになったら何かお返ししたいです」と心から感謝の思いを伝えてくれました。でも母の口から出た言葉は「お返しはあなたのそばにいる人たちで困っている人にしてあげれることをしてあげて。」というものでした。
それを話すとわかってくれる方々もいます。日本人の根底にある考え方なのでしょうか?でも、今は出したお金の分はいただく。それ以上のサービスを期待する。
労力に見合ったものを要求する傾向にあるなあとさみしい感じます。
目の前の方を助けてあげたお返しは無償でいい。助けられた思いをほかの方々へつなげていくこと。日本人の考え方の良い所として伝えていきたいと思います。
灰色からの手紙
2019.2.6
“灰色からの手紙”という絵の具のセットを既成のもので済ませるか、あるものと手作りのものでそろえるか?を考えるエッセイが載ってました。私は小学校の習字の道具を思い出しました。私の時代はそんなにセットとして数多く既製品があったわけではありませんがクラスの半分くらいは既製品のセットでした。私は叔父たちが使った硯のお古と家にあったカバン。さすがに筆は買ってもらいました。その中で硯の袋を汚れてもいいように使い古したタオルで袋を母が手作りしてくれていました。もしかすると見た目はみすぼらしく見えたかもしれませんが私にとってはとても嬉しい、母の心使いでした。みんなと一緒じゃなくてもいい。誰かのおさがりでもいい。そこに見た目だけではない思いを認められるようになっていたいと思います。
今は作るよりも安くて便利なものがあふれています。時間をかけるよりもお金で解決できるほうを選んでしまう空気があるように思えます。その中で、教育、子育てだけは手をかけ、時間をかけることを惜しんではいけないと思います。コンビニですぐに手に入る卵焼き。少し焦げ目のついた不格好なお母さん手作りの卵焼き。心と体が豊かに育つのはどちらでしょう?忙しい時に何度かコンビニ弁当、カップ麺に頼ってもいいと思います。ただ、それを習慣にしないように気を付けたいものです。お母さんの手作り卵焼きは幼児期の心も育てます。
庭しんぶん 第一こどものとも社監修2月号のエッセイの感想です。