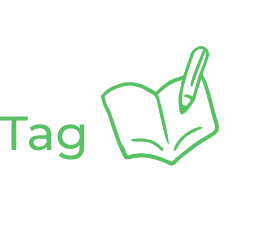固まってていいよ
2019.11.22
5歳のR君がお母さんに「お母さん。固まってていいよ。」と言ってくれたことを聞きました。
主婦の皆さんは朝から夜寝るまで、食事の事、家族の着ていくもの、持ち物の事、洗濯、明日の用意等、多岐にわたって準備し、予定を確かめてお子さんやご主人の1日1日が平和に過ごせるよう、配慮しています。きっとお子さんの前でも、忙しく、気配りをしながら、動き回っている姿があるのでしょう。
そして乳幼児はできるだけ母親が自分の方に向いていてほしくて、要求してきます。用事がなくても何か作って自分の方に向けようとします。そこで信頼関係を築いているので、それも大切なことでもあります。でも、R君はお母さんに対して、「固まってていいよ」と言えました。お母さん、今は何もしなくていいよ。お母さんの時間にしていいよ。という意味で言ってくれたというのです。大きく一つ成長したと感心しました。自律の一歩ですね。
そして、もう一つ。忙しい生活の中で、ふと、立ち止まるときがどんなに大切なことか。次へ次へと仕事をこなしていく流れを一度ストップさせて、周りを、自分を見つめてみること。そんなに急ぐ必要はなく、明日のことは明日心配すればよいこともたくさんあって。自分の心に向き合う時間をゆっくりとる事。固まる時間を私も作っていこうと思います。R君ありがとう。
みんなが仲良く暮らせるように
2019.11.15
「みんなが仲良く暮らせるようにならないものでしょうか?」とニュースキャスターが言われていました。当園のクリスマスペイジェントにも「みんな仲良く暮らせるようにならないかなあ」というセリフを開園当初から使っていました。
教育や人命救助の現場で行われているいじめの報道。耳を疑ってしまいます。いじめをしてはいけない!と教えなければならない大人たちが行っているいじめ。聖書には「自分の敵を愛しなさい」「隣人を自分と同じように愛しなさい」とあります。自分の敵とまで言わなくても意地悪されたり、嫌なことをされたら、同じくらいのことを仕返ししたいと思いますが、意地悪されたら親切でお返ししなさいと説きます。自分ができているか?と言われたら、難しい所です。大人の背中を見て育つ子どもたち。すべての人を自分と同じように愛することはできませんが、害を与えたり、傷つけることをお互いに避ける努力をしていけば、いじめは少なくなるのではないかと思うのですが…子どもたちにいじめるなという前に大人たちがまず自分の周りの方々と良い関係を結んでいく努力をしなければならないですね。自分の反省も含め、皆さんが仲良く暮らせるように!切に願いつつ、努力します。
出会いに感謝
2019.11.5
先日、北光幼稚園の創立100周年記念礼拝、記念講演に出席させていただきました。記念講演の講師は私が元北星学園幼稚園教諭保母養成所でお世話になった担任でした。(今から40年前です。)懐かしくお会いし、まだまだお元気なお姿に励まされる思いでした。ご自身の研究を探求し、今も現役で研究されているお姿はとても刺激になりました。そして、今現在同業者であり、やはり担任をしていただいた友と一緒に講演前にあいさつに行きましたが、今も幼稚園教諭として立っていることを伝えられたことがとても誇りに感じました。そして、一番感謝なことは、保育者、教諭となって35年以上たちますが、その原点で出会った方にお会いできたこと。そして、一人でここまで来たとは思っていませんが具体的に、自分の今現在の土台、根っこのところで支えられていたことを再確認させられ、感謝が溢れました。今豊かに祝福されていることは、もうずっと前から計画されていたことで、偶然ではなく、導かれていたんだと。出会いの一つ一つが自分を造り、今を生かしていただいているのだと感激しました。
教諭の仕事をさせていただいている以上、自分自身も相手にとって良い出会いだったと感じてほしいと、更に自分が学びの手を休めてはいけないと襟を正されました。
中学生訪問
2019.10.25
今日は中学3年生のお兄さん、お姉さんたちが家庭科の授業の中で訪問してくれました。紙芝居や魚釣りなど、手づくりをして何日も丁寧に準備をしてきてくれたことが伝わってきました。グループに分かれて、それぞれがよく関わられるように、考えられていました。園児たちもお兄さん、お姉さんたちととても仲よく喜んで遊んでいました。卒園生たちも何人かいて、その成長ぶりには目を見張るものがありました。子どもたちの成長を見るのはとてもとても嬉しいことです。
一つ気になったことがありました。それは事前に家庭科の先生と打ち合わせをしていた時のことです。自由な時間があると何をしていいかわからず、不安になる子がいるということでした。園児たちは毎日、許された守られた空間と時間の中で自分の好きなことを自分で選び、気のすむまで遊びこむ。そこには何の縛りもありません。失敗もします。何回もやり直しをします。友達とのトラブルも日常茶飯事です。その中で迷惑をかけてはいけないことや、破ってはならないルールがあることを学んでいきます。そこから、生きていく意欲、好奇心、想像力などが育ち、主体的に生きていけるようになると考えます。せっかく育った芽が枯れてしまわないか心配になります。自由な発想や行動が互いに受け入れられる環境を自分自身が作っていくこと。少数、多数に関わらずそれぞれの思いが受け止められていく社会になってほしいと願います。
忘れ物
2019.10.18
よく、忘れ物検査などをして忘れ物をしない意識を高めたり、時間割をなんども確認する習慣を付けたり。保護者が低学年のうちはしっかり見てあげたり。でも、今の忙しい社会においては、保護者の方々も子どもたちの準備に対してままならないところがあるようです。忘れ物をしないことは大事なことですが、幼児期、小学校の低学年のうちの忘れ物は取り返しがつくものです。取り返しがつくうちに何度か、忘れ物やほかの失敗をすること。そしてその失敗をどう乗り越えるか?というを経験して育ってほしいと思います。忘れ物をしたとき、失敗したときの思いは皆さんも経験があると思います。それぞれに感じ方は違いますが、自分が我慢しなければならないことや、周りに迷惑をかけたことへの申し訳なさ、どうやったら取り戻せるか?考えること。失敗には非認知能力をフルに使わなければならない面が多々あります。あえて、忘れ物をする必要はありませんが、子どもたちが自分で準備して、いくつかの不足があった時に全てを周りが整えるのではなく、失敗する経験をすることが大切です。そこから学ぶこと、成長することがたくさんあります。失敗する恥ずかしさを乗り越えながら、人は大きくなります。マニュアルでしか考え、行動できない大人に育てるのではなく、子どもたちには予想外のことが起こった時に目の前にある状況から、打開策をみつけ、進んでいけるよう、クリエイティブに育ってほしいと切に願います。
先生、あのね
2019.10.3
「せんせい、あのね、この靴下おかあさんに買ってもらったの。」
「せんせい、あのね、今日ばあばとプール行くの。お兄ちゃんとおねえちゃんも。」
「せんせい、あのね、これ虫なの。でね、魚になっちゃうんだよ。そしてね」
満3歳の子との会話です。向き合ってゆっくりじっくりきいていると、延々続きます。お話はとりとめもなく、本当の出来事とそうでないものとが混ぜ混ぜになっていますが、楽しそうにたくさん話してくれました。
聞きながら、この時期の子たちはこうして自分の話を聞いてもらいながら、自分の存在を確かめているんだなあと感じました。この子にとってこの記憶はきっとひとかけらも残らず消えてしまいます。でも、受け止めてもらったことは魂、情緒が受け止めます。乳幼児期の大切なところはここだと思います。何気ないまいにちですが、その中で普通の事。朝起きてごはんがあって、洗濯されたものを着て、遊び、1日を過ごす。周りに自分をまもり、育んでくれる方々がいてくれる。その日々の中で健全に心身は成長していきます。その積み重ねを通してお子さんたちは自分が保護者の方々に愛され、存在していていい、大切な者だと自己肯定していきます。今の、今しかない乳幼児期をできるだけゆっくり向き合う時間をとり、楽しんでください。私たちも微力ですがお手伝いさせていただきます。
オータムコンサート
2019.9.30
先日、かおり幼稚園を会場にして久米小百合さんの”オータムコンサート”を行いました。(主催は北広島福音キリスト教会です。)久米小百合さんとは以前「異邦人」が大ヒットした久保田早紀さんです。童謡や讃美歌を中心に1時間半ほど歌い上げてくださいました。チケットは好評で立ち見が出るのでは?と心配したほどでした。アンコールに「異邦人」を歌っていただきました。文化的にあまり豊かではない北海道の北広島市に本物に触れることのできる1日でした。私は勤め始めてすぐのころ、職場の新年会の余興で同僚たちと「異邦人」にふりを付けて踊らせていただきました。ある方は初めてのエレクトーンの発表会で弾いたのが「異邦人」でした。と1つの曲に皆さんそれぞれエピソードがあるものですね。遠くは中標津からも来られた方がいらっしゃり、歌ってくださった久米さんに、そしてお越しくださった方々に心から感謝いたします。
夏休み
2019.7.25
夏休みの季節ですね。私の小中学校時代は周りには両親共働きの方はあまりいませんでした。(すみません。50年近くも前のことです。)長い夏休み。朝から晩まで遊んだ思い。そして時間を持て余した思い。退屈ではあったけれど、その中でいろいろなことを考えたり、試行錯誤して時間をつぶしたり…今思えば貴重な時間だったのではないかと思います。幼稚園で預かり保育、学童保育をしながら、できるだけ、ゆったりと家庭にいるように過ごさせてあげたいと思いつつ、人数が多いとそれだけでも確保してあげるのが難しい状況があります。
低年齢の子にはスキンシップの大切さが言われますが、小学生にも言えると思います。実際にハグをしたり、触ったりしなくても、帰宅したときに今日あった出来事を聞いたり、一緒にいる時間を特別に持つこと等。中学生になったら、さらに何を考え、何を感じているのかを何時も気にかけていることを家族の方々は伝え続けていくことが大事だと思います。日頃お忙しい日々をお過ごしの方々が多くなり、子どもが夏休みになってもお仕事はそうはいかなく、時間が取れないかもしれませんが、お子さんと向き合う時間をこの夏大切にしてみてはいかがでしょう。
お泊り会
2019.7.12
今、お泊り会の真っ最中。女の子のシャワータイムです。昼間はJRに乗って新さっぽろの科学館で見学体験。プラネタリウムも見てきて感動して帰ってきました。自分たちでつくったカレーを食べて、これからお楽しみタイム。そのあと、ずっと宇宙探検をテーマに遊んできたゆり組さんは天体望遠鏡で星座を見る予定でしたが、あいにくのお天気で、ちょっと残念。それでも夜になっても大好きなお友達と一緒で、いつものおうちとは違う環境に、わくわく感が続いています。明日の朝、目覚めた時には一晩幼稚園に泊まったという達成感で自信を付けたきらっきらの目を見開いて、おはようございます。この瞬間が私は大好きです。それぞれが自分の乗り越える山を越えて、成長していくこと。助けてあげる所とじっとこらえて超えられるまで、見守ること。子どもの成長はそれぞれです。そして、今日のその子と充分向き合えるといいですね。忙しくて1日、1日あっという間に過ぎてしまいますが、向き合える時を大切にしていきましょう。
火災避難訓練
2019.6.26
昨日は火災避難訓練でした。消防の方々にも来ていただき、消防自動車は2台も来てくれました。火事を発見し、初期消火をし、子どもたちの誘導、消防署への通報等、一連の流れは毎年行っていても緊張します。また、実際に火事が起きた時にはどう動けるか?訓練をちゃんと生かせるように取り組みたいと考えています。また、園児たちは練習だとわかりつつも非常ベルの大きな音が怖かったり、いつもと違う動きに戸惑ってりと、初めての子たちにとっては訓練といっても真剣な取り組み事項です。
一通り終えて、消防自動車を見せてもらって、質問をしました。Sちゃんが「消防自動車は怪獣をやっつけられますか?」と聞きました。消防のおじさんは「やっつけられるように頑張ります」と答えてくれて一安心。大きな消防自動車は火事からも、危険からも私たちを守ってくれます。でも出動しない事件事故のない平和な日々を心から祈っています。また、子どもたちの小さな質問?夢も守ってくれたことに心から感謝です。命を守られる事と、自分の命を自分で守ることの大切さを知った1日でした。